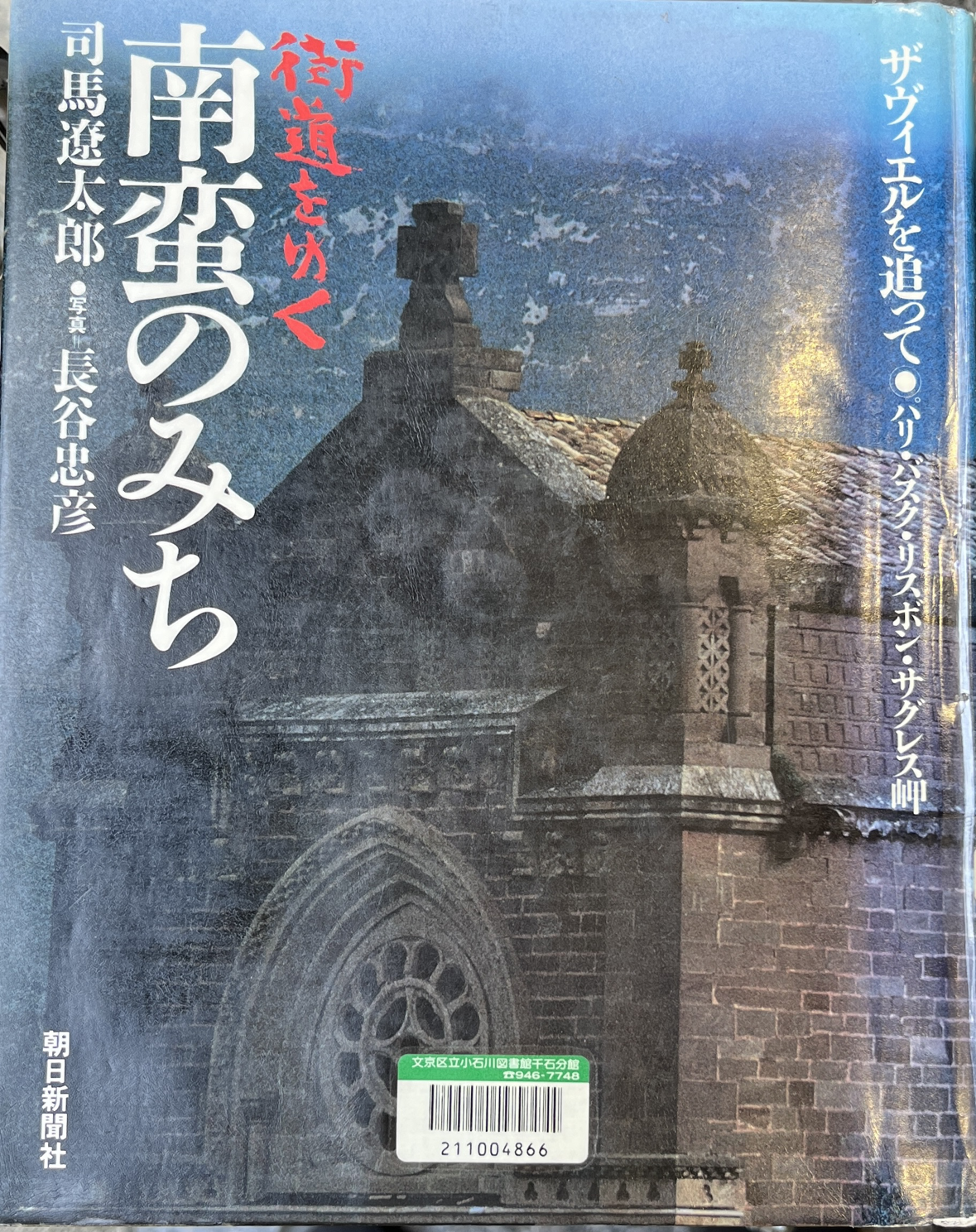第50回『もう愛の唄なんて詠えない』さだまさしエッセイ

『もう愛の唄なんて詠えない』さだまさしエッセイ
さだまさしの語るエピソードは、いつも具体的で心がほっこりする。
さだまさし 「高校野球の季節に思い出す一戦 “53対1”のコールドゲーム その1点の重みに、僕は救われた」(抜粋)
夏の高校野球が始まると思い出すゲームがある。それは、昭和62年7月1日に岩手県営球場で、地方大会の開会式直後の2試合目に行われた。強豪、盛岡商業高校と無名の岩手橘高校の1戦だった。
結果は53対1という大差の五回コールドゲームで盛岡商が勝った。
勿論、僕はその試合を目撃している訳ではない。翌朝、新聞の朝刊に「歴史的大差」というトピックスとして小さな記事が載ったものを読んで知った。ただこの時僕は、ある新聞に載ったこの試合のスコアボードの写真を見て、極めて強く興味を惹かれた。いや、53点の方ではなく1点の方にだ。今でも時々、地方大会の話題にこういう大差の試合が報じられることがあるが、ほとんど大差で負けた方のチームの得点は0点だ。力の差とはそういうものだ。だがこの試合では、相手にたった五回で53点を奪われるほど弱い岩手橘が、何故か1点を奪っている。しかも、その1点はなんと4回裏に得点していたのだ。一体どうして得た1点なのか?お情けで貰った点なら却って侮辱だし、哀れ過ぎる。歴然とした力の差のある戦いでは考えられない程重い「1点」なのだ。
興味が湧くと、いても立ってもいられない僕は、この試合のスコアのコピーを手に入れた。そうして安比高原のホテルの珈琲ショップで珈琲を飲みながら、そのスコアを開いた。マッチ箱を四つ、塁に見立ててテーブルの上に配置し、マッチ棒を動かしながらあたかも棋譜を読むように、この試合を机上に再現した。心が高鳴り、わくわくする様は上質のミステリーを読むようだった。
一回表、盛岡商は岩手橘の投手、藤原を攻め、9安打7四球7盗塁に8つのエラーがからみ、打者25人で21点を奪う。二回表、更に2安打と1エラーで2点。岩手橘はこの裏2安打を放つが0点。すでに23対0。三回表は15人の打者、6安打2四球5エラーで11点。岩手橘は三者凡退。ここで34対0。手を抜かない盛岡商も立派だ。四回表、3安打2エラーで3点を奪い、この回ですでに37対0となる。
そして、いよいよ僕のこだわった四回裏が来る。岩手橘、1アウト後、投手藤原がこの日、盛岡商の記録した、たった一つのエラーで出塁する。ここで5番セカンド下村(幸)が左中間三塁打を放ったのだ。後で聞いたことだが、この時、球場全体がどよめき、大拍手が起きたそうである。それはそうだ。正々堂々たる1点だ。僕も珈琲をひっくり返しそうになって拍手した。涙がこぼれそうになる。こいつら、ちゃんと出来るじゃねえか、と。しかし、次の五回表、盛岡商は13安打6盗塁に3エラーがからんで16点を加え、ついに53対1というコールドゲームが成立した。
本来遊撃手だった藤原君がこの日、投手のいないチームにあって、度胸が良いというだけで初登板し、五回で260球を投げた。被安打33四死球12奪三振2だった。神様は、意地悪なのか優しいか分からない。投手がいなくて急遽登板した十八歳の少年、藤原君をこれほどいじめなくても良いではないか、と思うが、それでもたった1点だけ返したホームを踏んだのはその藤原君だった。
この暫く後、この一戦を揶揄する記事が週刊誌に出た時、僕は激怒した。揶揄した筆者は、余程野球を知らぬか冷酷で残忍だ。繰り返すが、53対0なら凡戦だ。しかしこの、37点をリードされた後の四回裏の1点の本当の重みは、野球好きなら、いえ、人間なら分かる筈なのだ。この1点によってこの試合は名勝負となり、僕の胸に深く刻まれたのだ。
実はこの頃、折から僕は、中国で撮影した映画による二十八億円の上る個人の借金に苦しんでいた時期で、人生の重みと夢の重さを両手にぶら下げて途方に暮れていた頃だった。だからこの岩手橘高校の1点は、何より「最後まであきらめるな」という僕への強いエールに思えた。37対0でも、たった1点を取りに行こうとするのが「生きる」ことだよ。「捨てるな」と。
夏の高校野球。それは、只一度も負けなかったたった一つのチームと、たった一度しか負けなかった四千幾つのチームで出来ている。
僕は苦しい時いつもこの53対1のゲームを思い出す。そして自分に言うのだ。結果でなく中味だ、と。
さだまさし『もう愛の唄なんて詠えない』より