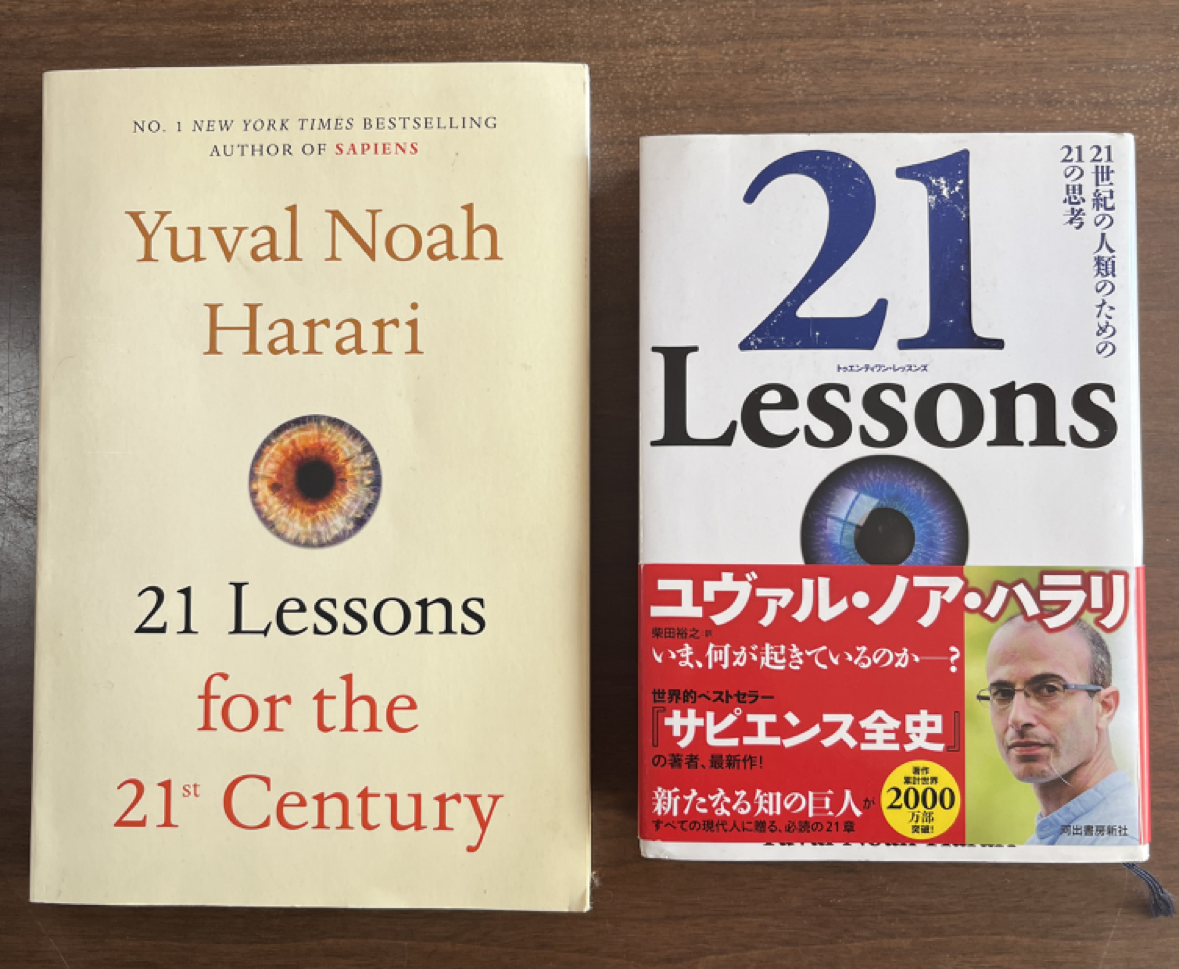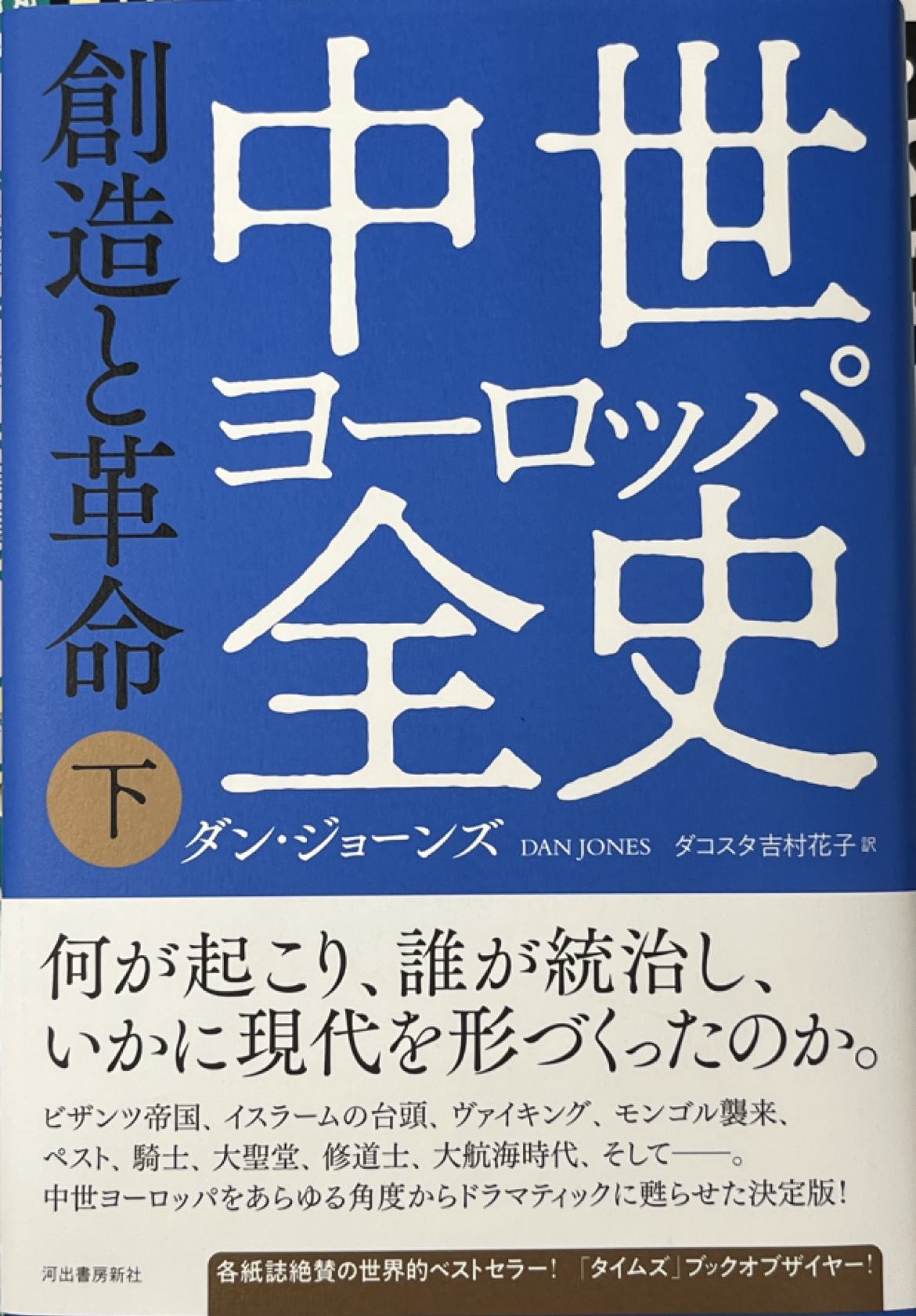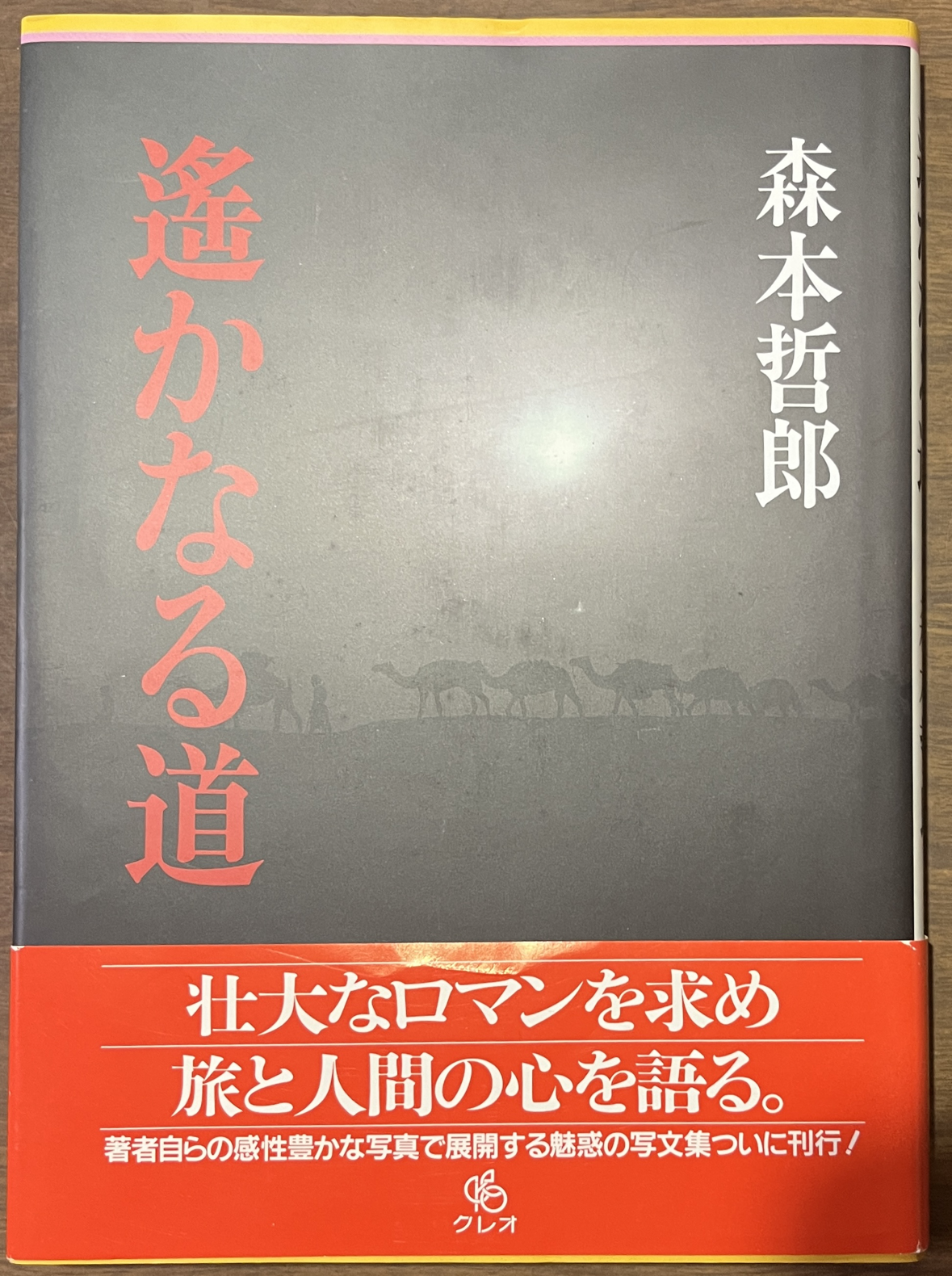第5回『古句を観る』および『蕉門の人々』柴田宵曲著


『古句を観る』および『蕉門の人々』柴田宵曲著
「子(柴田宵曲1897-1966)は中学を中途で退学したといふ乏しい学歴しか持たなかった。
『古句を観る』 森銑三解説より
しかしそれから図書館に通って、自分の好きな本を読み、自分で自分を作り上げたのだから、ちょっと真似の出来ぬ人だった。・・・
『古句を観る』の古句は、元禄時代の無名作家の手になつた俳句ばかりを集めてゐる。それでゐてその個々は今日出しても清新な句ばかりなのだから、元禄時代にかやうな句も出来てゐたのかと驚かされる。
宵曲子は古い俳書をも丁寧に読んで、さうした句ばかりを集めてゐたので、その点に子の鑑識が窺はれる。
・・子ならでは作ることの出来ぬ書物であつた。
・・宵曲氏は一歩退いて世を送らうとしてゐた控え目な人で、そのことは一部の人々に知られてゐるのに過ぎない。
子は何ともいはれぬ気持ちのよい人で、その実力は子を知る限の先輩同輩の等しく認めるところであつた。」
「年末から年始にかけての数日を家に閉籠って、二階で日向ぼっこしたり、下の居間で炬燵に当たったりしながら、柴田宵曲氏の新著『蕉門の人々』に読み耽った。
それが私には近頃楽しいことだった。『蕉門の人々』には、俳諧随筆という冠称が附してある。
『蕉門の人々』 森銑三解説より
序文には、「ただ作品を通して直接その人の面目を窺おうという、おぼつかない試みの一に過ぎぬ」と断ってある。
しかしながら本書の著者は古句を心解し、味読することにおいて、いわゆる研究家を任ずる人びとの到達し得ない世界に住している。
おぼつかない試みというのはもとより遜辞で、著者の態度はあくまでも手堅く、また手強い。
作品そのものを仲介として、蕉門の諸作家に肉薄し、膝詰談判に及ぼうとする。
そこに息の詰まりそうな緊張した気分さえ伴っている。
本書の内容は、祖述ではなくて創作である。
随筆とは銘打ってあっても、ただの漫文や雑文とはわけが違う。
全体が渾然とした作品に成っている。その点に及び難い感を抱かせられる。」
これは、柴田宵曲氏の仕事を紹介するに相応しい森銑三氏の名文だ。
無名の俳諧師でも佳句は佳句。芭蕉、蕪村や一茶オンリーの専門家の追随を許さない。
著者からは江戸俳諧の本当の味わい方を教えてもらった。
極上のワインを味わうようなコクのある文章も魅力だ。