雑司ヶ谷墓地 東池袋
冨田鋼一郎
有秋小春

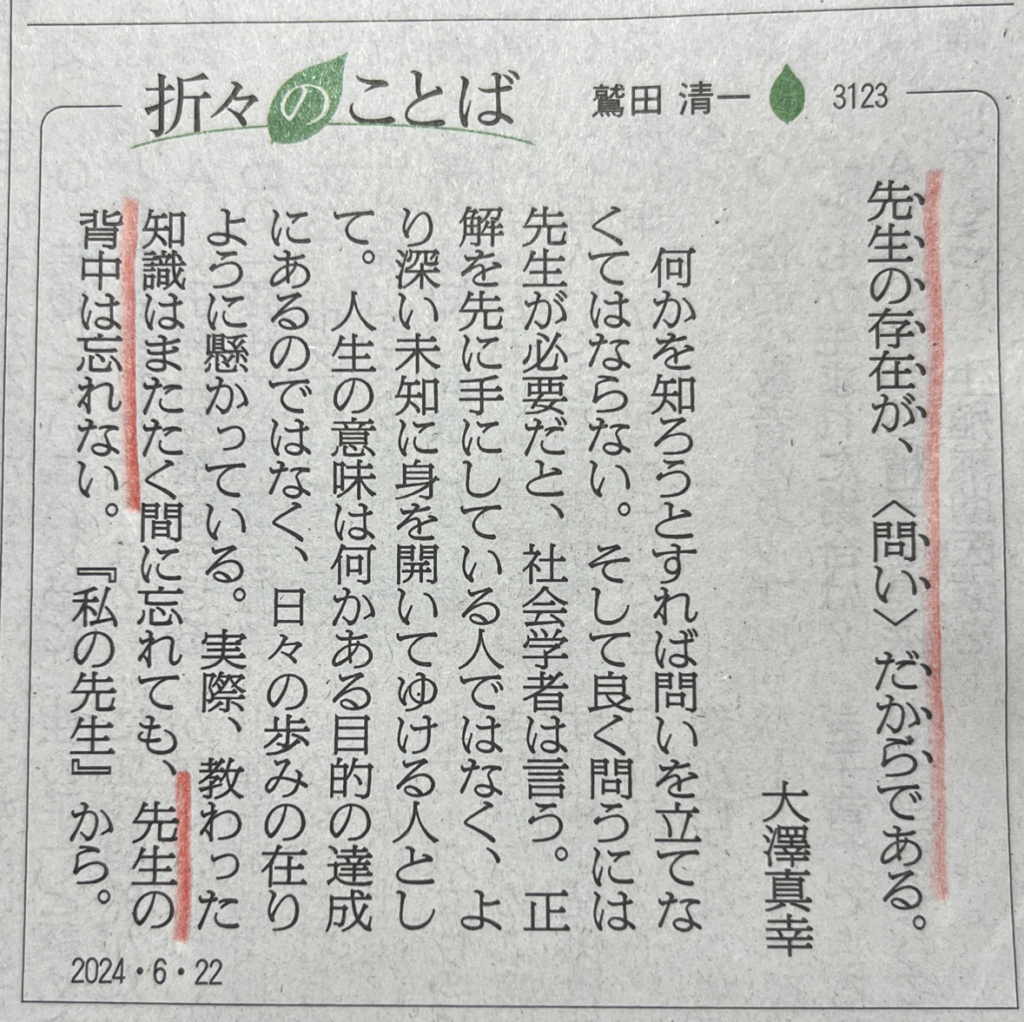
よい先生とは何か?
この大澤真幸氏の先生の定義のようなことばは含蓄がある
「先生の存在が、<問い>だからである」 大澤真幸
何かを知ろうとすれば問いを立てなくてはならない。そしてよく問うには先生が必要だと、社会学者は言う。
正解を先に手にしている人ではなく、より深い未知に身を開いてゆける人として。
人生の意味は何かある目的の達成にあるのではなく、日々の歩みの在りように懸かっている。
実際教わった知識はまたたく間に忘れても、先生の背中は忘れない。『私の先生』より
@@@@@@
『先生はえらい』で内田樹氏が、噛んでふくむめるように繰り返し述べていたことに通じる
なぜ勉強しなければならないのか?
バツかマルか、白か黒かに囚われている人がいる
白黒のはっきりしていることは、世の中のごく一部でしかない
先生はいったい何をどこまで知っているのか、先生は知っているのに自分は知らないと思い込む(誤解する)ことで、生徒は何かを学んでしまう
まなびの成立と、先生との出会いは同時に起こる
これが自ら問うということ、学びの主体性ということの本質だ
学びには、先生の存在が必要だ
生涯の恩師は誰にでもいる
未知のことに対してどこまでも知ろうとする、学びの姿勢は先生の存在が起動させ、終生持続する
私にとっては、そのような「先生」を一人あげろといわれたら、あのひとしかいない(という勝手な思い込み)