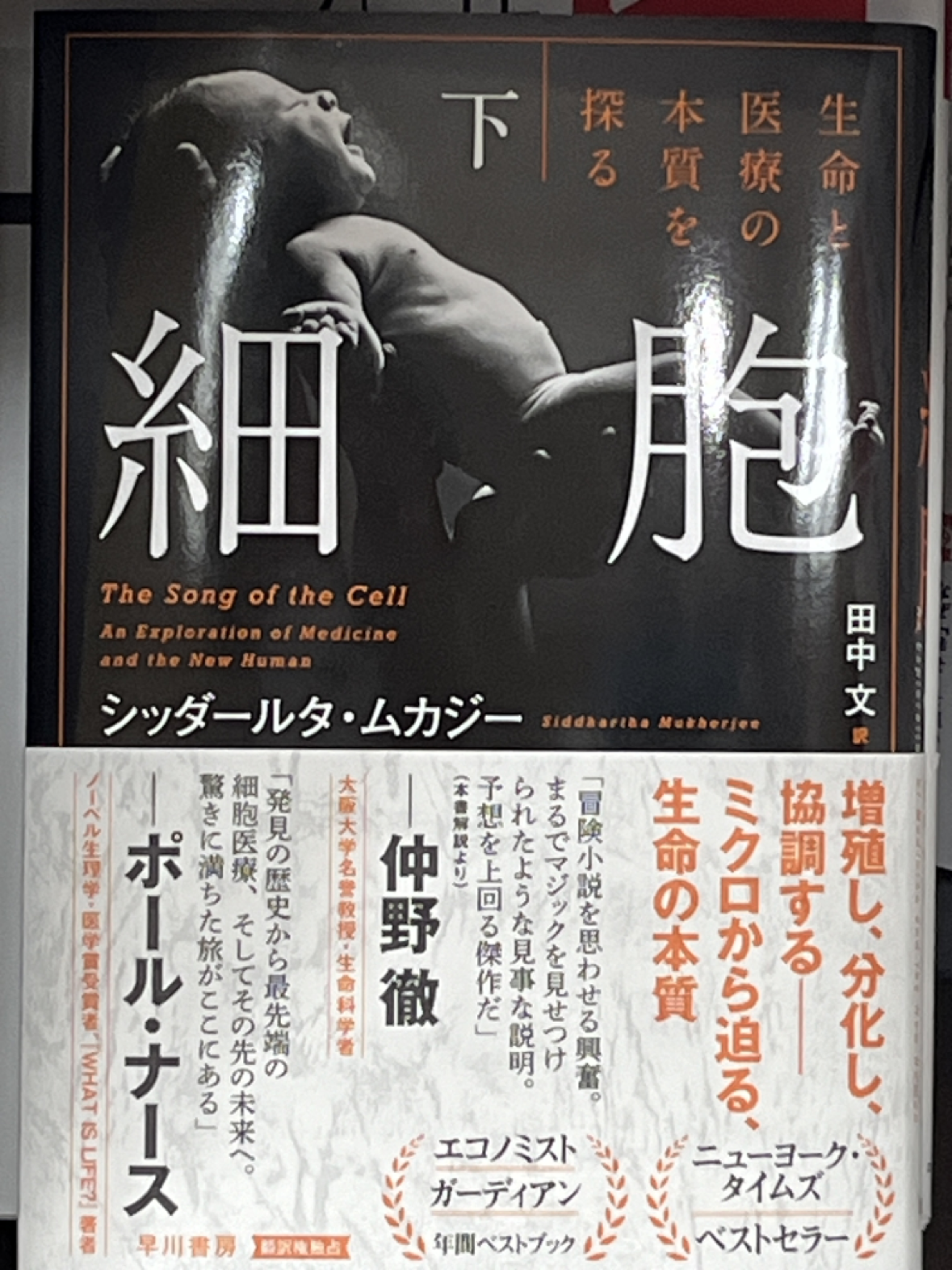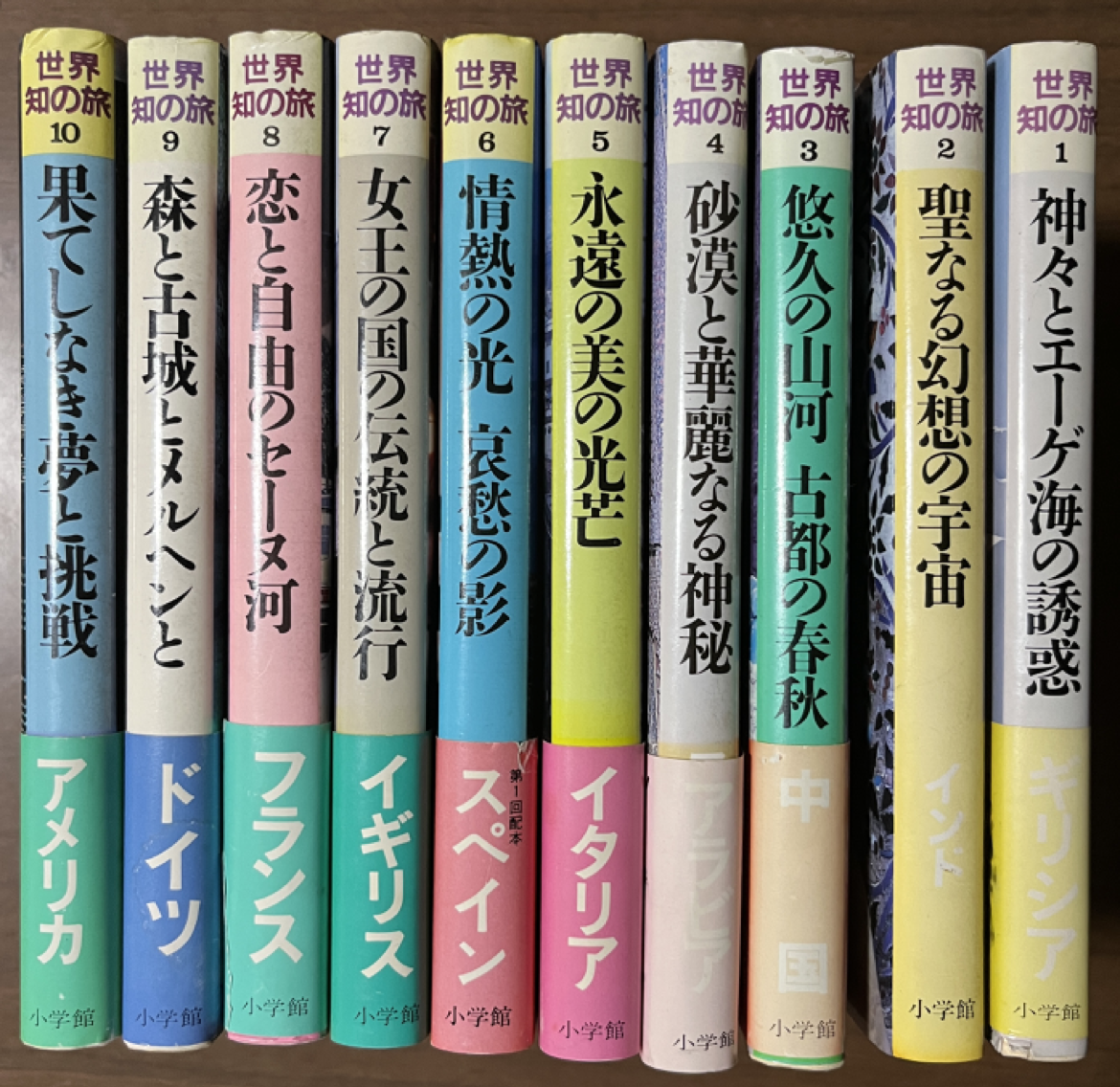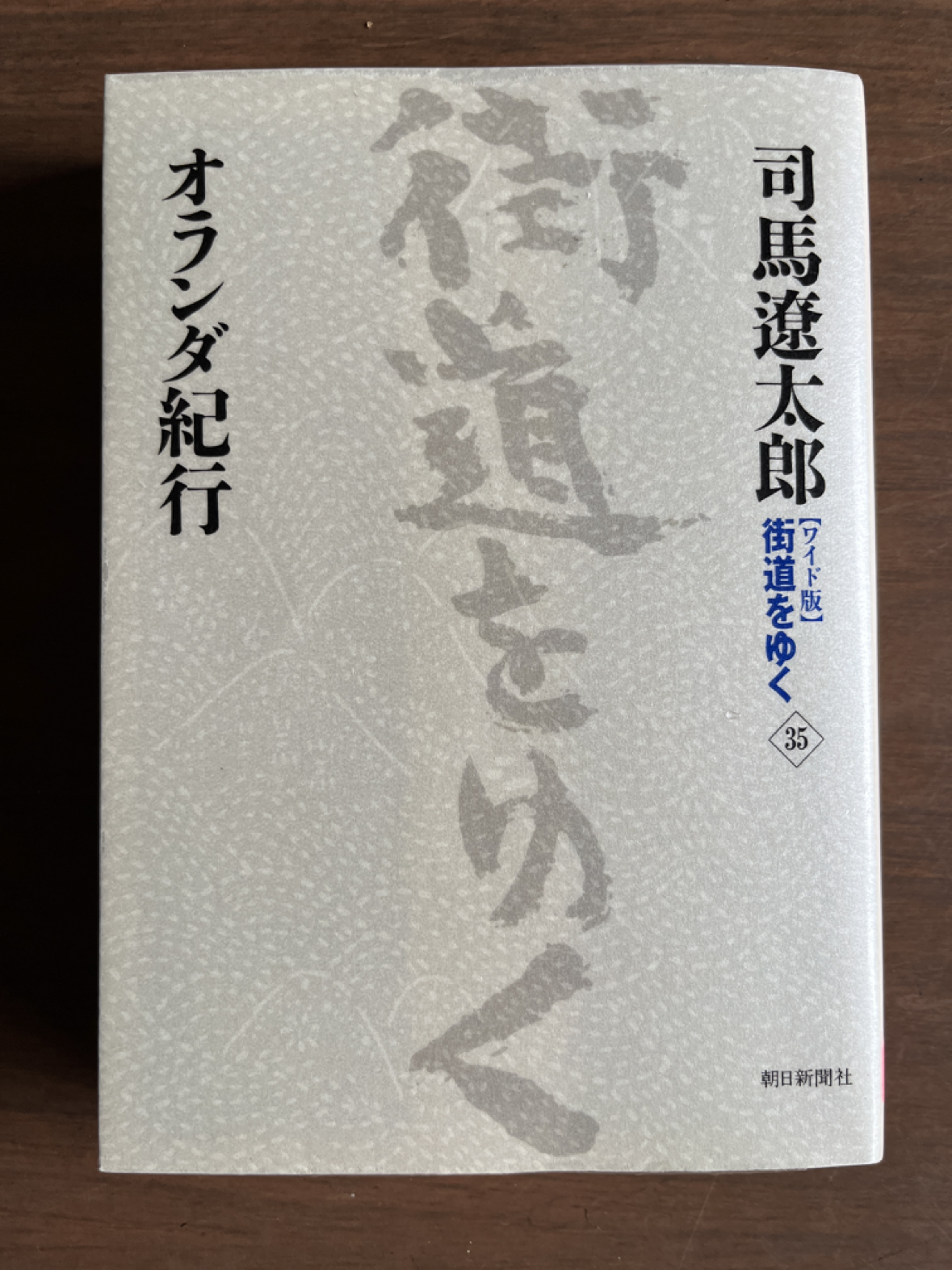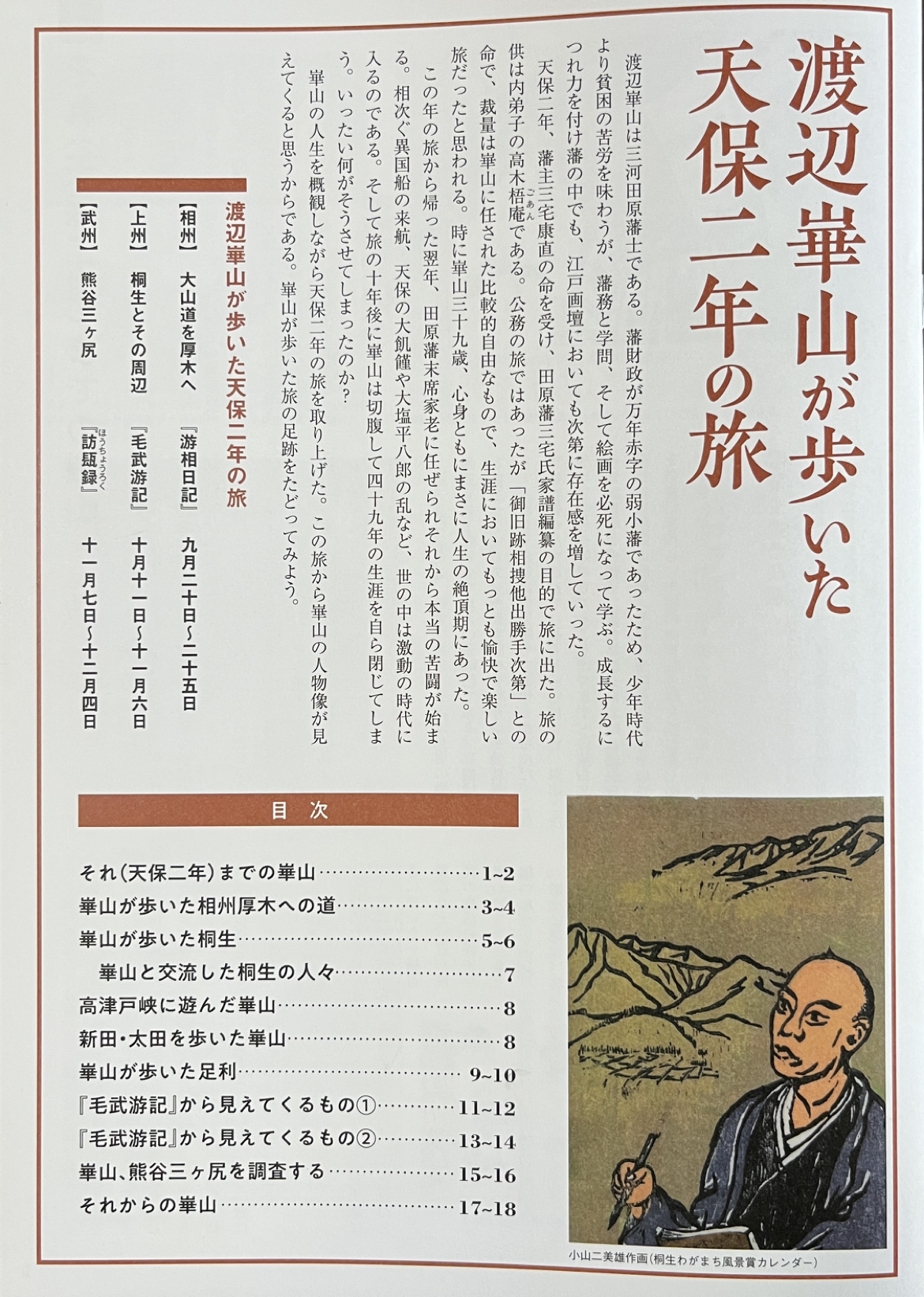読書逍遥第139回 『地図で見るバルカン半島ハンドブック』

地図で見るバルカン半島ハンドブック』
世界的テニスプレーヤーのジョコビッチはセルビア出身だ。バルカン半島も中東と並んで、遠い日本からは分かりにくい。
半島の国境で区切られた地図を眺めても、国名とその並びすらおぼつかない。
1989年鉄のカーテン消滅後、ユーゴスラビアは凄惨な長い過程を経て解体された。1990年代、国連高等弁務官の緒方貞子さんがコソボで苦労した地域。
「歴史と地理」を合わせながら理解に努めるしかない。
長い歴史から世界を眺めると、「統一と離散」「統合と分割」を繰り返している。
1991年のソビエト連邦解体と90年代のユーゴスラビア解体、どちらも分割の動きだ。効果的な統治が可能なより小さな単位に「分割」された。「分割」とは、より小さりな単位に権限を移譲させること。
同時に、世界は「統合」の方向にも強い力が働いている。経済のグローバル化、デジタル革命によって世界が結びつきを強めている。
分割によって権限移譲、繋がりによって集約が、互いに相反するベクトルの力がこれほど同時に起きている時代はなかった。
グローバル化した地球は、分割と統合のマグマによって成り立っているのだ。
==============================================================
民族紛争は世界中で起こっていますが、争いの火種は時に領土であり、経済的な問題であり、差別や格差であり、そして宗教問題です。
これらすべての問題を内包しているのが、旧ユーゴスラビアで起きた紛争でしょう。バルカン半島に位置するユーゴスラビア王国ができたのは20世紀初め。
「ユーゴスラビア(南スラブ)」と名づけたのは、オーストリア=ハンガリー帝国から脱し、南スラブ人の国をつくろうという意思の表れであり、「ユーゴスラビア王国」に改称する以前は、「セルビア人・クロアチア人・スロベニア人王国」(セルブ・クロアート・スロベーン王国)でした。
長年オスマン帝国やハプスブルク家の支配に苦しんできた南スラブの人々にとって、独立は悲願だったのです。
しかし、同じスラブ民族であっても、中心がセルビア人というのは、クロアチア人にとっては面白くない。第二次世界大戦中にクロアチア独立国が独立したのはそのためです。
しかし、第二次世界大戦終了後、旧ソ連の支配を避けてスラブ人の国としてやっていくためには、力をあわせなければなりません。
アメリカの援助のもと、独自の共産主義国家として歩みだしたユーゴスラビア社会主義連邦共和国は、セルビア、クロアチア、スロベニアだけでなく、ボスニア・ヘルツェゴビナ、マケドニア、モンテネグロという共和国の連合体となりました。
「六つの共和国、五つの民族、四つの言語、三つの宗教、二つの文字」という複雑さ。さらにセルビアのなかにはヴォイヴォディナとコソボ自治州があり、始まりからすでに、「問題が起こらないほうが不思議!」という国だったのかもしれません。
ギリシャ、ブルガリア、そしてユーゴスラビアのあるバルカン半島は、「ヨーロッパの火薬庫」と呼ばれる紛争の多い場所。オスマン帝国とハプスブルク家の支配によって民族や宗教の構成が複雑化したためで、それは現代においても変わりませんでした。
ユーゴスラビアのなかの同じスラブ人でも、クロアチア、スロベニアはカトリックで、文化的・宗教的に西ヨーロッパに近い。セルビアは正教会で、「ザ・スラブ」といったところ。
セルビア語とクロアチア語は日本の方言よりも近いくらいであるにもかかわらず、宗教が違うために文字が異なります。
こうした事情で1990年代に入るとクロアチア、続いてスロベニアが独立を望み、ユーゴスラビア紛争が始まります。
多数派であるセルビアとの対立構造でしたが、あくまで社会主義国家ユーゴスラビアの独自路線を目指すセルビアと、EU加盟を願うクロアチアの対立、クロアチアを支援するドイツの存在がその背後にありました。
続いて、ボスニア・ヘルツェゴビナが独立を求めます。ボスニア・ヘルツェゴビナの人たちも、同じセルビア語、クロアチア語を話しますが、かつてオスマン帝国の支配を受けた際に改宗したイスラム教徒。
したがって、「クロアチア人でもセルビア人でもない別の民族」と認識されています。宗教が民族を形成した1つの典型例ですが、これが悲劇を生みました。
イスラム教徒であってもキリスト教徒であっても、「ユーゴスラビア人」として、ごく普通に生活していたのに、ある日突然、宗教が違うだけで、隣人や友人と民族的な敵対関係になり、奪いあい、殺しあうことになる……。
紛争が泥沼化するなか、セルビア内コソボ自治州に住むアルバニア人が独立を求めて蜂起しました。バルカン半島の紛争は、ヨーロッパ・カトリック(クロアチア人)VSスラブ・正教会(セルビア人)VS中東・イスラム教(ボスニア・ヘルツェゴビナ、アルバニア)の三つ巴でもありました。世界の紛争の縮図にも思えます。
国連、EU、NATOも介入したすえ、2006年にモンテネグロが独立したことでユーゴスラビアは完全に解体されました。
意外と知られていない、東ヨーロッパに残るオスマン帝国の影響
20世紀まで存在したオスマン帝国支配の名残は、日本のビジネスパーソンが想像するよりも大きいものです。
たとえば、ハンガリーなど東ヨーロッパの国のキリスト教の教会を訪れると、「文様や修飾がまるでモスクのようだ」と感じることがあります。
そこで調べてみると、「やっぱりオスマン帝国の頃のモスクを改装した教会だ」とわかったりするのです。
オスマン帝国はイスラム教への改宗を強要しなかったため、ヨーロッパ在住者でムスリムとなった人は、ボスニア・ヘルツェゴビナとアルバニア以外にはあまりいません。
それだけに、この2つの国はヨーロッパの異分子として扱われることになります。
私は2017年にボスニア・ヘルツェゴビナの首都サラエボを訪れましたが、明らかにヨーロッパ系の顔立ちをした人が、モスクで祈りを捧げていました。
残虐な殺戮もあったユーゴスラビア紛争は、いまだ生々しい負の記憶です。サラエボを訪れた際、私は現地の日本人から、こんな話を聞きました。
「ここでも現地スタッフを数十人単位で雇用していて、みんな同じような言葉を話すし、仲良くやっています。でも、どんなに円満に見えても、絶対に民族や宗教は聞けませんよ。『彼は金曜日になるとちょっとだけいなくなるから、イスラム教徒かな? 金曜の集団礼拝に行っているのかも』と思いますけれど、うかつに触れられない。方言的な感じで『この人はセルビア人かな』と思ってもクロアチア人だったりしますし、結果的に自然にわかるのはいいけれど、話題にするのはタブーなんです」
イスラム教というオスマン帝国の残した大きな影響が「多様性」というプラスに働かず、「民族・宗教紛争」というマイナスにつながってしまったことは残念でなりません。
しかし、歴史を振り返れば、中国の清王朝が漢民族の文化を取り込みながら発展したように、異なるカルチャーを受け入れることで成功した事例がたくさんあります。
ダイバーシティの時代を生きる私たちは、旧ユーゴスラビアの歴史を学ぶことで「多様性」から生み出すべきものは対立ではないということを知ることができます。
なぜいま、「民族」を学ぶべきなのか?
「ダイバーシティが重要」「世界の多様な価値観を理解すべき」……。このような声を聞くことが最近増えましたが、ダイバーシティやその前提となる多様な文化・価値観を理解するためには、民族について知っていることが重要です。
しかしながら、世界96カ国を巡り、様々な国や民族の人たちと仕事をしてきた私からすると、日本人の民族への理解――いわば「民族偏差値」は、世界最低レベルだと思います。
日本人は単一民族ではないものの、限りなく単一民族的です。みんな似ているし、争いはあまりないし、言葉もそう違わず、結婚・就職の差別も世界的に見ればとても少ない。
ただし、多様性がないから無知になり、発想が貧しくなります。多様であることが新たな文化を育み、イノベーションのもとになるのです。
元外交官が語る、“世界の紛争の縮図”旧ユーゴスラビアから学べること
山中俊之