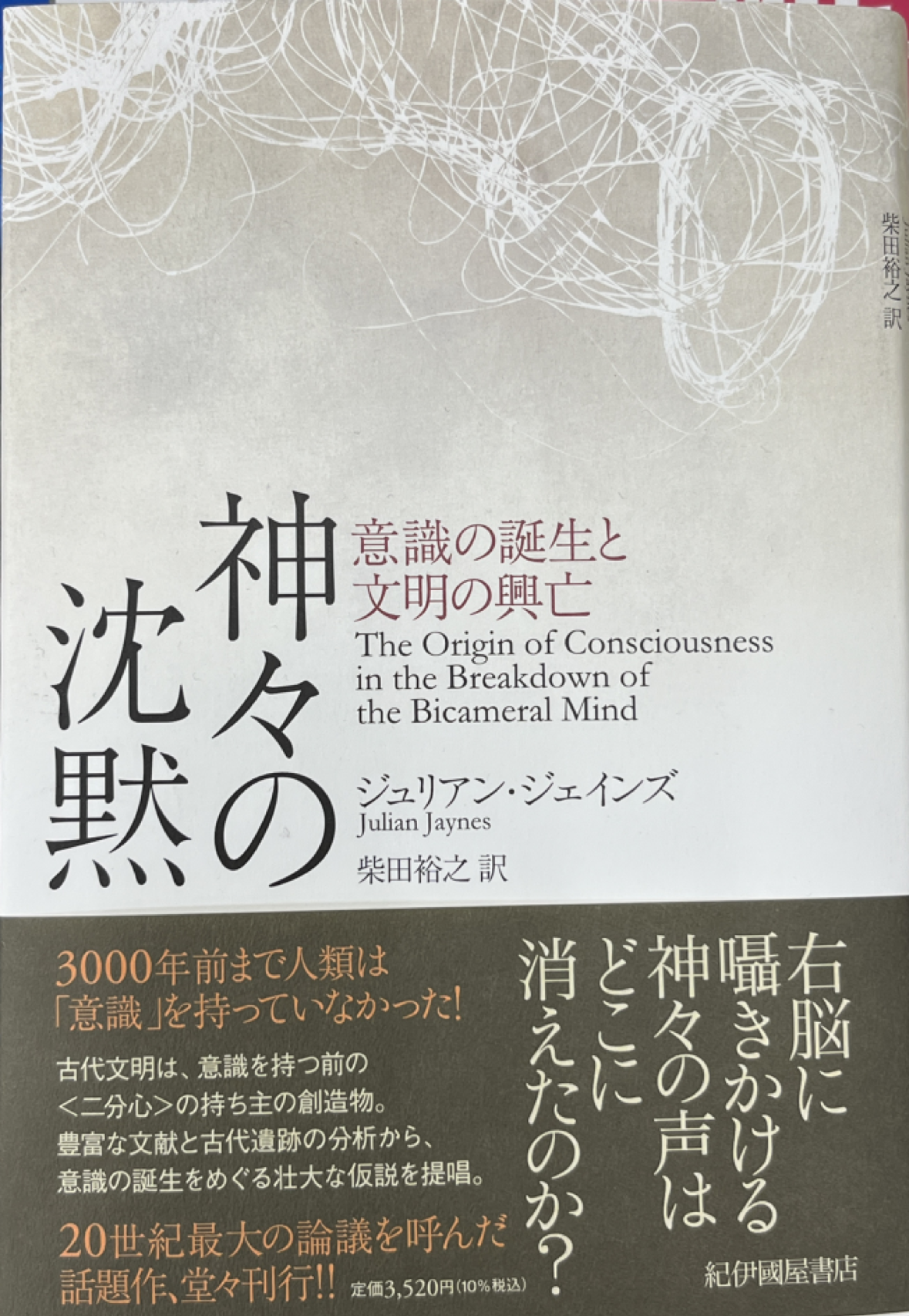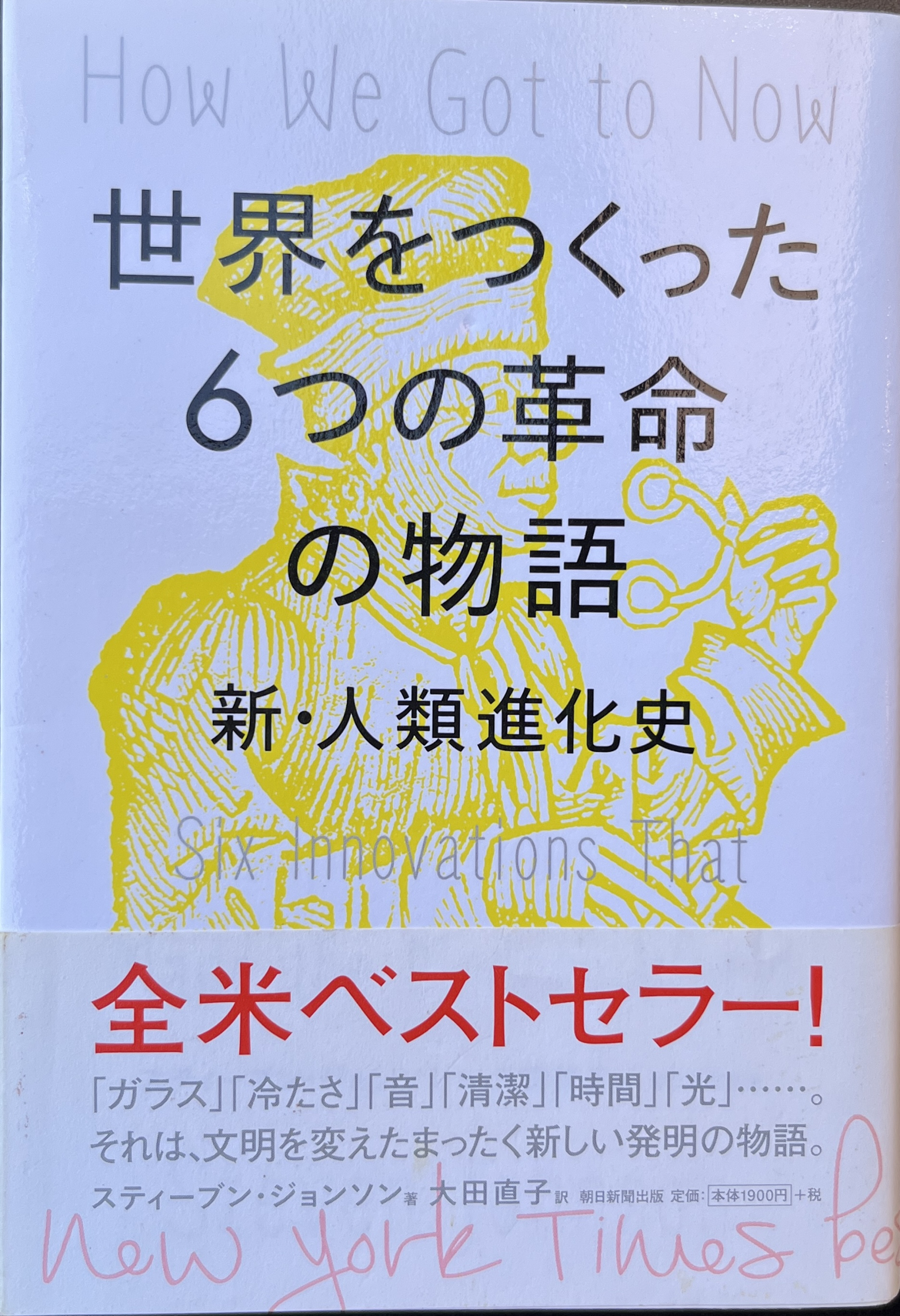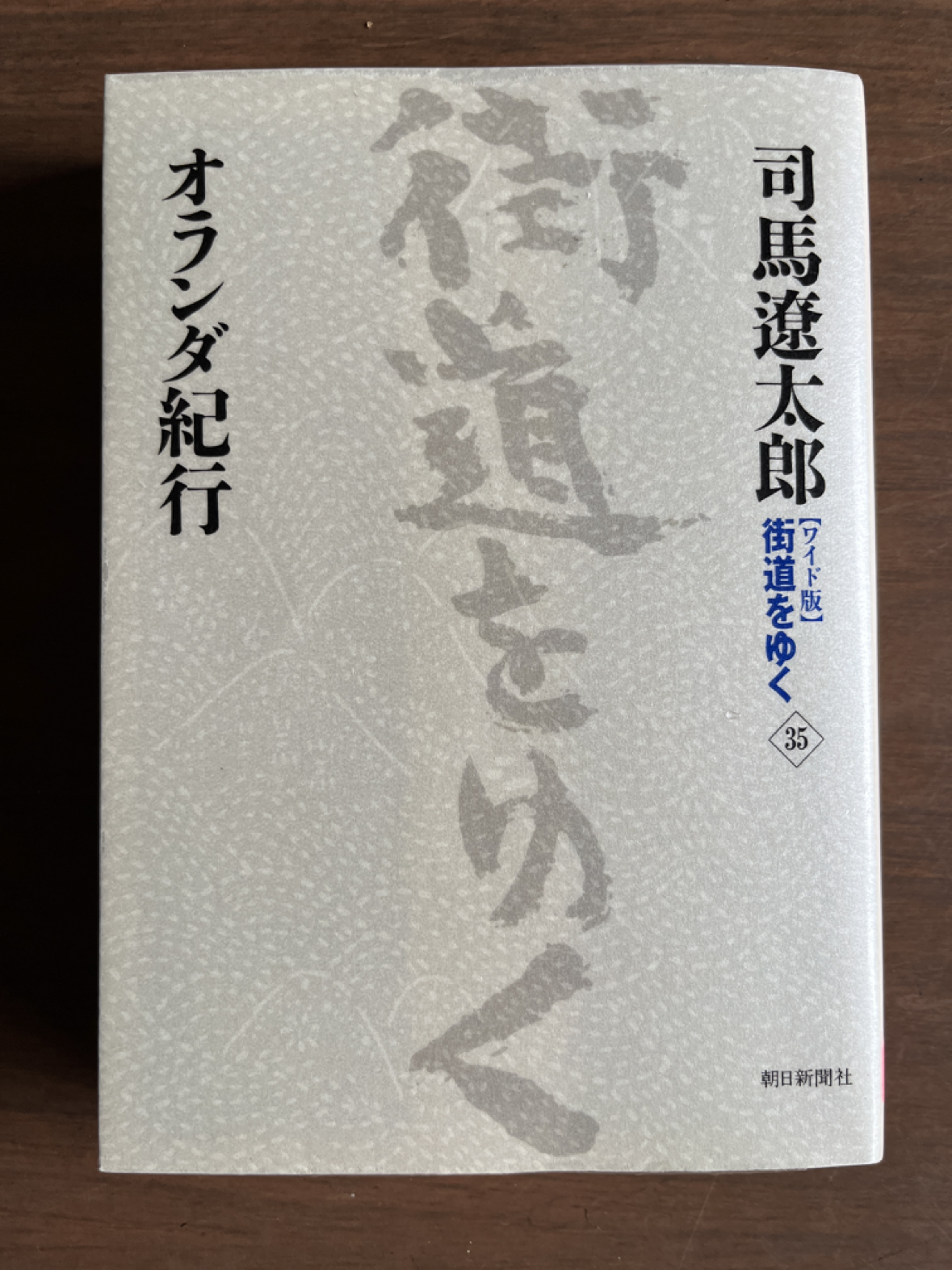読書逍遥第108回 『蝸牛庵訪問記』小林勇著
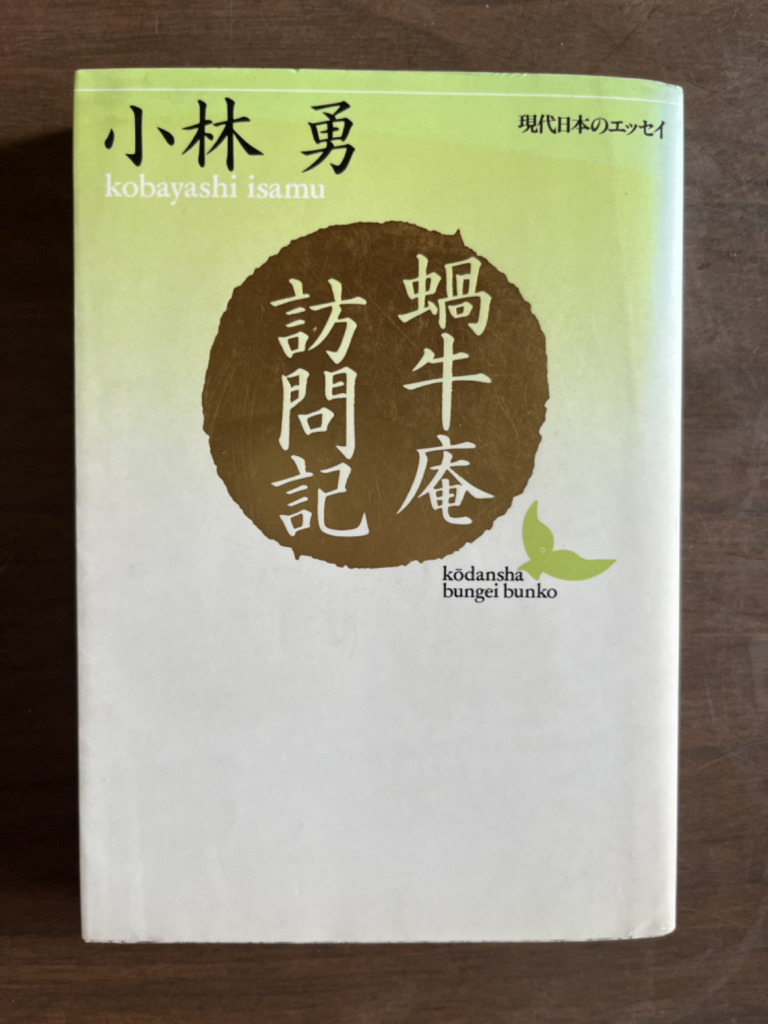
『蝸牛庵訪問記』小林勇著
幸田露伴(1867-1947)
小林勇(1903-1981)
蝸牛庵(がぎゅうあん)・幸田露伴と若き日の出会いから、その凄絶、荘厳な終焉の日までの“日常”の比類なき記録。該博な知識、不羈の精神、巨大な文学空間を展開する“文豪”露伴の、慈父のごとき姿をあざやかに捉える。
岩波書店の社員として小林が露伴の住む「蝸牛庵」(文京区伝通院)を訪ねたのは23歳の時。初めは門前払いされたが、通い詰めるうちに露伴は心を許し、小林は蝸牛庵にいりびたるようになる。二人は親子以上に歳が離れていたが、友に似た関係になっていった。
近寄りがたい露伴の懐に入り込むことができたのは、小林勇しかいない。次々と明かされるエピソードに、温かい交流をみる。
二つの例を挙げる。
☆☆☆
「故人今人・酒のみばなし」
(「小林勇文集」第十巻)
障子にうつっていた榎の枝の影がいつの間にか消えて、室は薄暗くなっていた。露伴はそのとき机の傍にひじ枕で横になり、その前に私はあぐらをかいていた。
今日もまた長居になった。階下では家族の人たちが夕飯の支度をしながら、客の分も作るべきかどうかひそかに心を悩ましているにちがいない。
露伴は私が帰ろうとし、もう少し引きとめたいときにはそういう姿勢で挨拶ができないようにすることがあった。しかし、今日は、私は横になったままの露伴に挨拶をした。
そして室を出ようとすると「ちょいとお待ち」といって立ち上がり、室の隅にある用箪笥の中から、紙の巻いたものを取り出し立ったままさらさらとそれをひらき、「これはどうだい」といった。何かの記号のようなものであった。
「先生、何ですか」ときくと、「酒という字だよ」といい、熱心に説明をはじめた。この字がどのように変わっていったかを考証したのちに、中国の有名な学者がどのように書いたかを露伴自身で模したものである。
巻紙は畳に渦を巻いた。室は暗くなっており、立ったままで露伴は説明を続けていた。巻紙の長さはおよそ三間に及ぶであろう。終ったとき、私はそれをくるくると巻き返した。
巻き終えたときにそれを内ポケットに入れて、「先生、これはぼくが貰います」というか早いか階段を駆け下りた。玄関で靴をはいている私に二階から露伴の声が聞こえた。「そうかえ、君は酒のみだからそれを持って行くというのかえ。」
****
『蝸牛庵訪問記』より
(昭和19年 露伴78歳 小林勇41歳)
私は数年前から絵を描くことに熱中していた。熱海へ来てからも私は絵を描いた。先生は日本間の方にいる。私は洋間の絨毯の上に紙をのべて、庭に咲いている椿の花などを描いた。
或る日、銭舜挙の鶏頭の図を模写していると、そこへ先生が来て「お前も物の形を少しは描けるようになった。二人で寄せ書きをしようか。」といった。そして先生は「君が竹を描き給え。僕が雀をとまらせる。」といった。そのとき私は、竹を描いてからそれに雀をとまらせるのは大変だから先生が先に鳥を描きなさいといった。すると先生が「竹があるから雀がとまるので、雀を先に描くのはよろしくない。」といった。
この数日間、毎日一緒にいて、なんとなくジリジリしていた私は、そういわれただけで腹をたてて、合作などしたくないといってしまった。先生は簡単に「そうかな。」といっただけで自分の室に入ってしまった。
☆☆☆☆