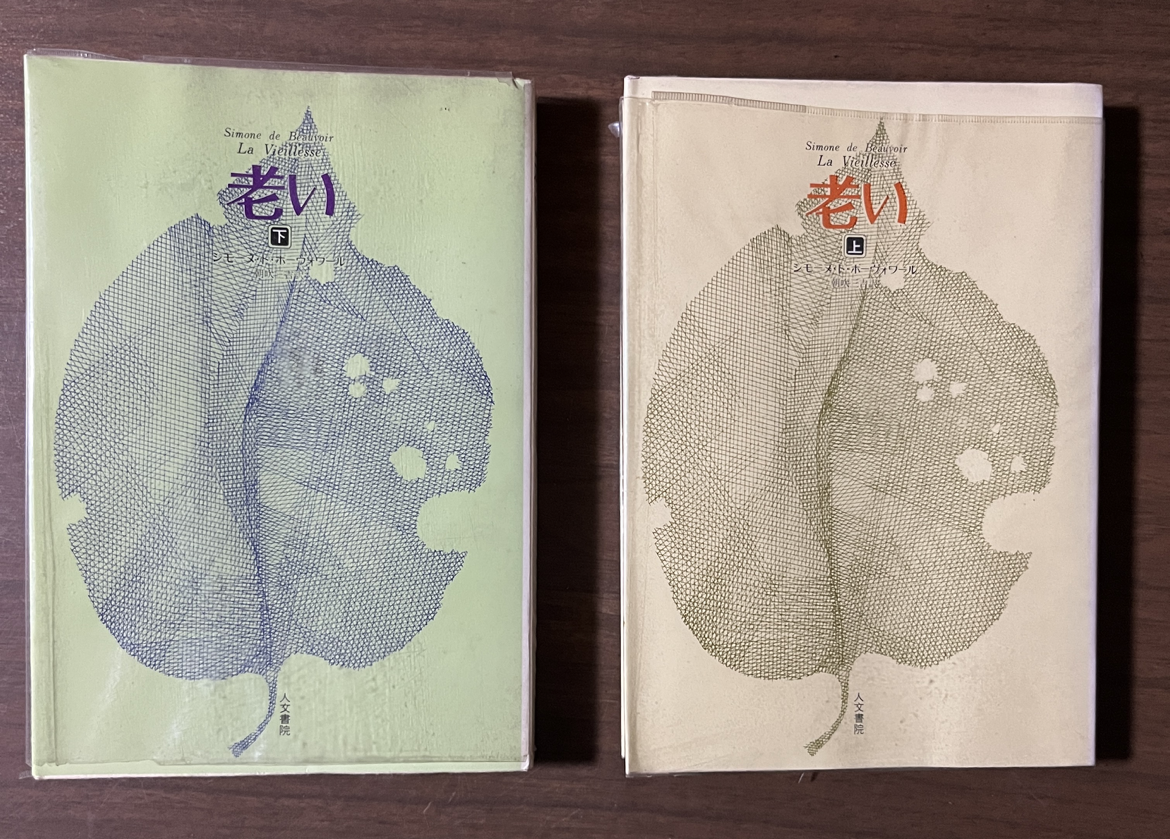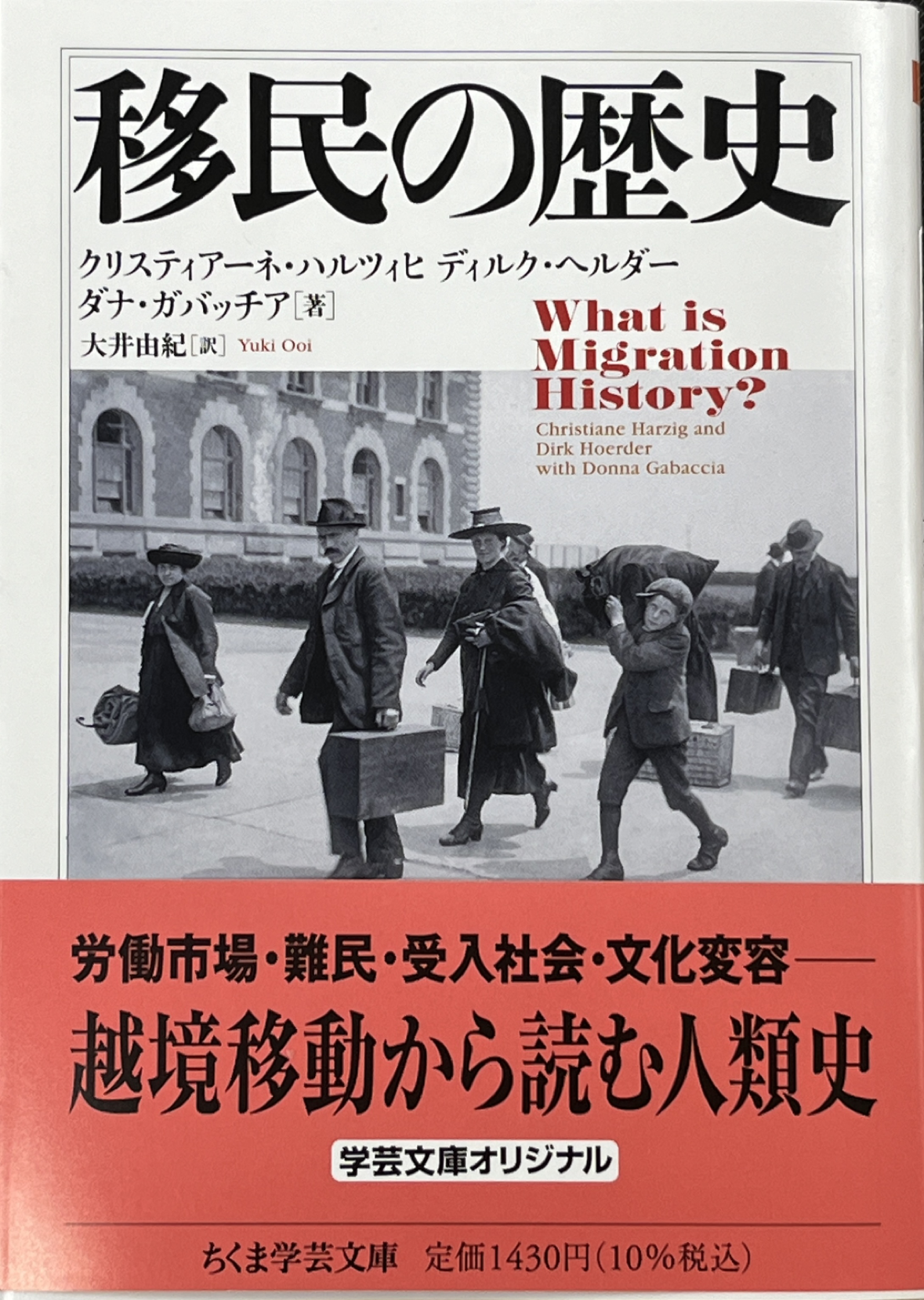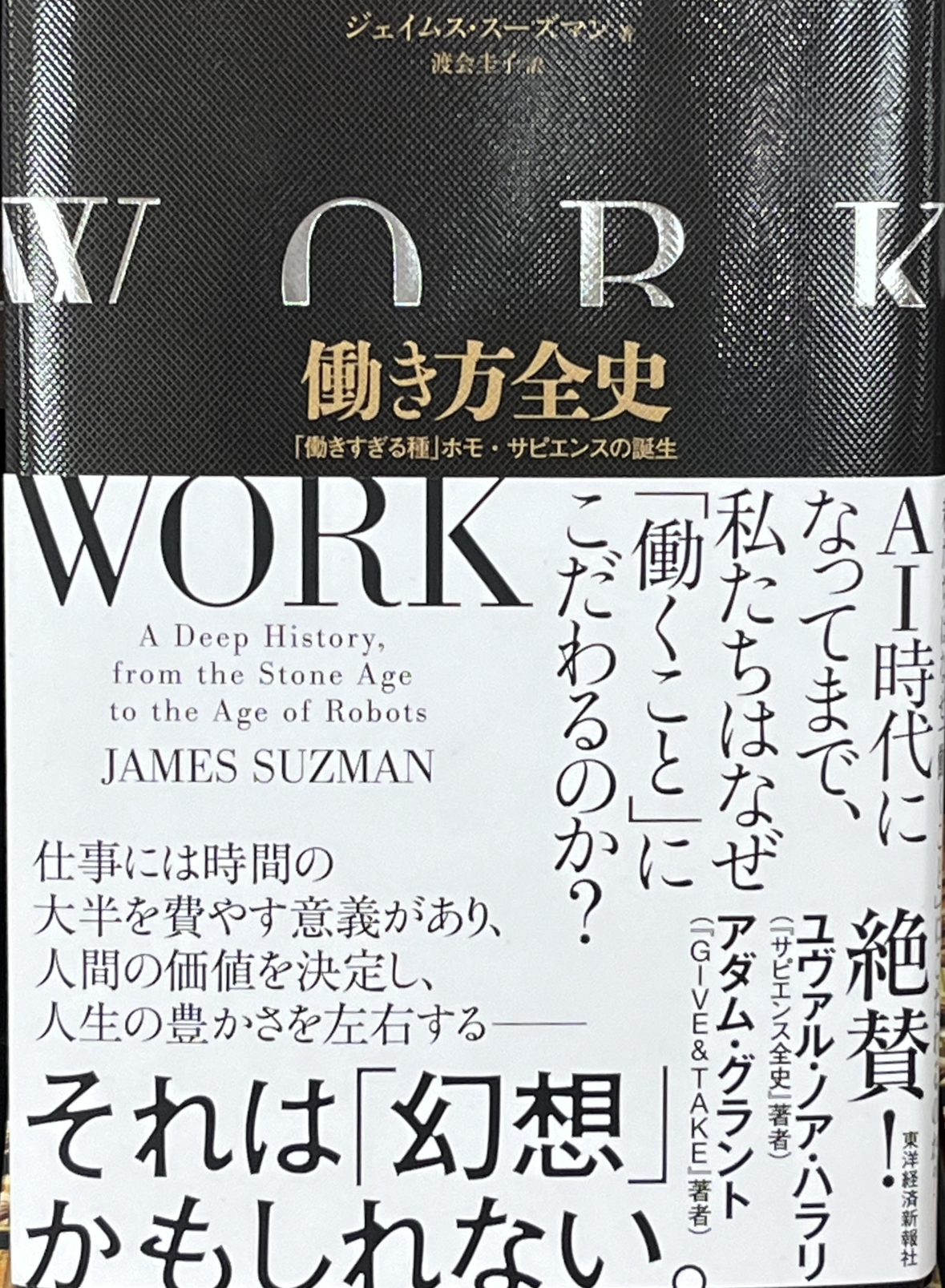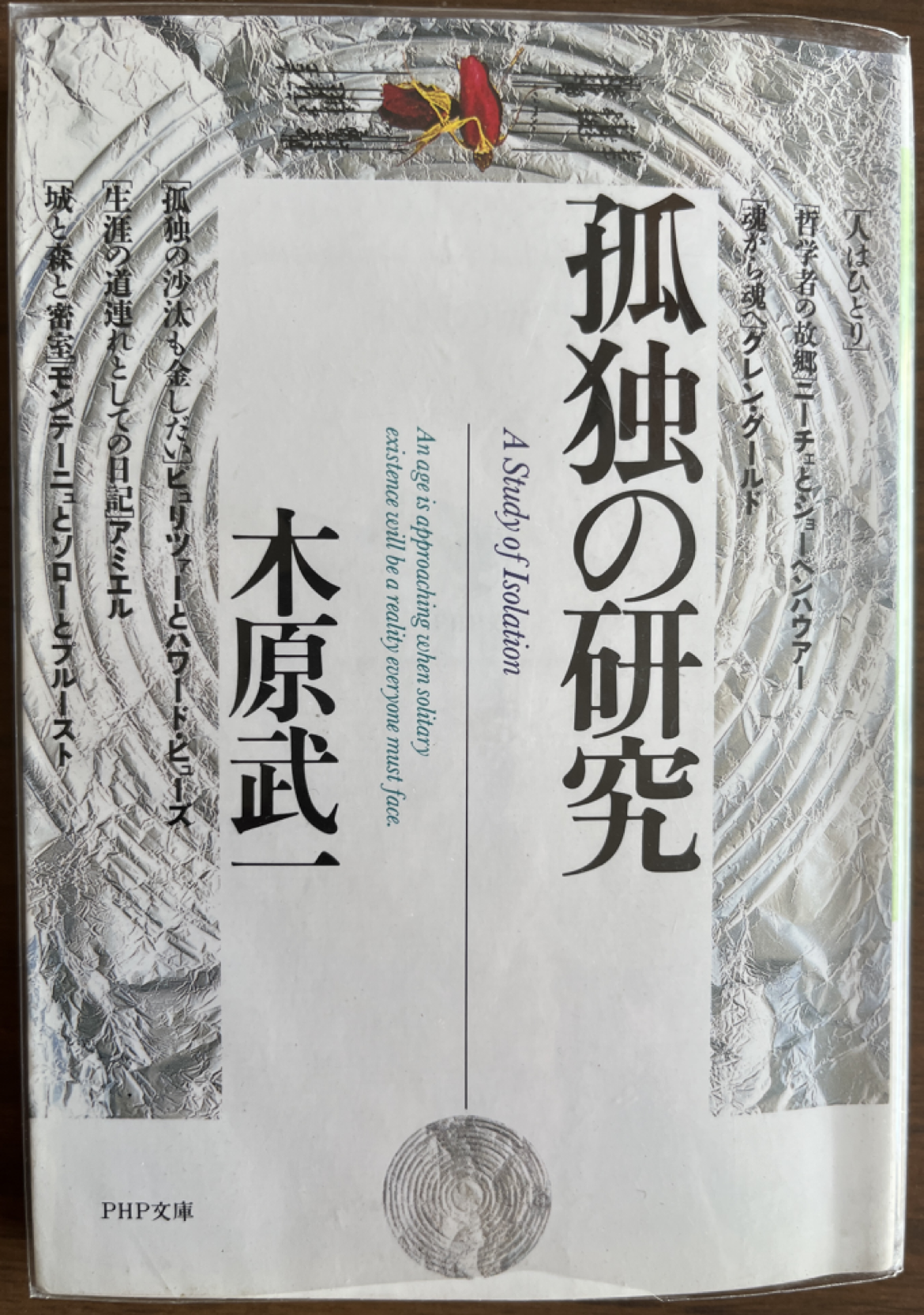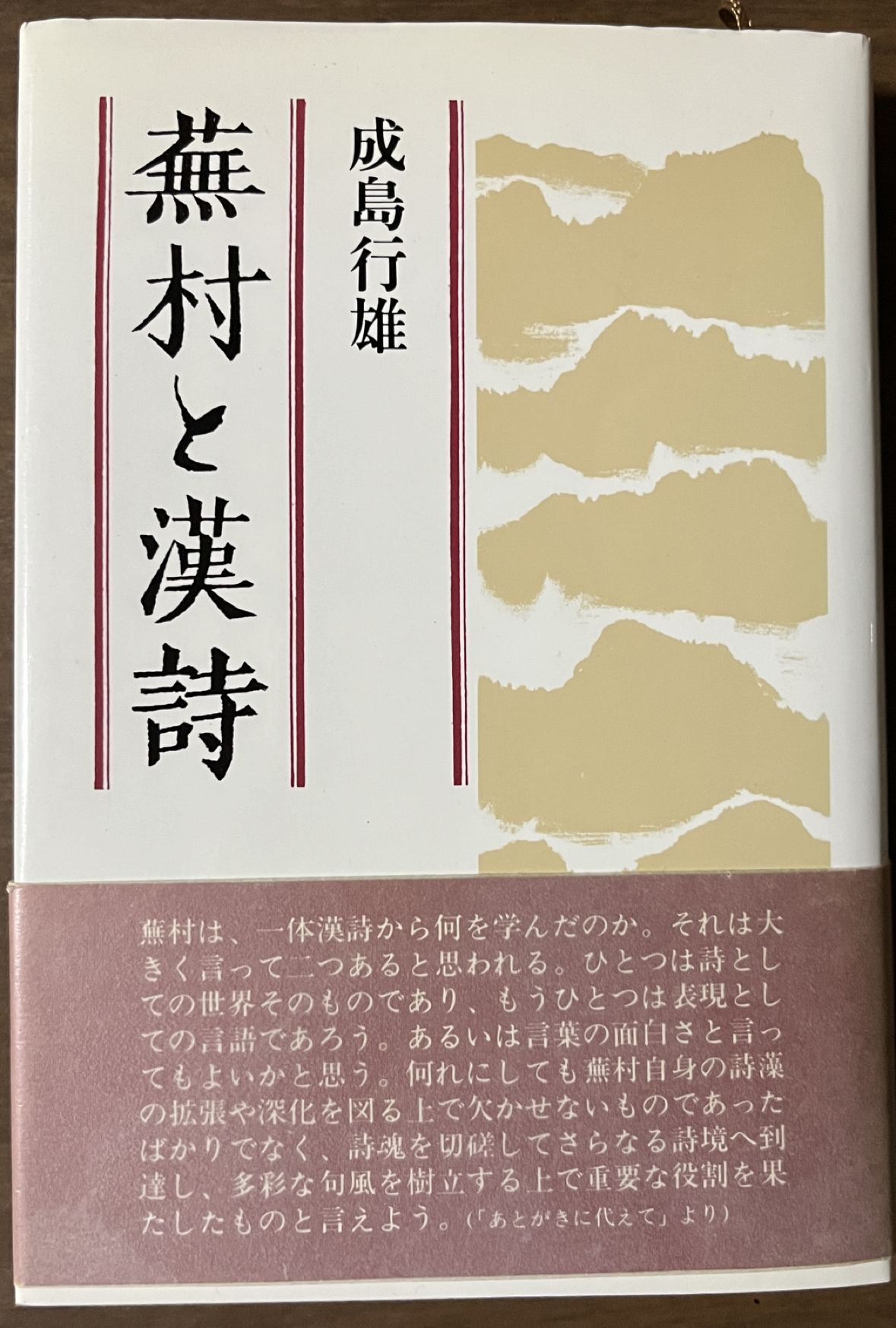読書逍遥第102回 『古句を観る』柴田宵曲著

『古句を観る』柴田宵曲著
俳句とはこのように味わうのか。俳句鑑賞の仕方を教えてくれた本。
俳諧といえば芭蕉、蕪村、一茶の名前ばかりを追いかける風潮に反して、江戸俳書を丁寧に読み込んで、無名作者の句だけを選んで鑑賞に及ぶ。
こんな作業は本当に俳諧好きでなければできない。巷の俳諧研究者ではとても敵わない。
本書は戦時中に出版された。驚くべきことに、時局を窺わせる言葉がでてこない。著者は古俳句とともに日々生きていたのだ。達意の文章の例でもある。
例えば、
⭕️ 杉菜喰う馬ひつたつる別かな 関節
「餞別」という前書がついている。如何なる人が如何なる人を送る場合か、それはわからない。わかっているのは送られる方の人が、これから馬に乗って行くらしいということだけである。
名残を惜しんで暫く語り合ったが、どうしても出発しなければならなくなって、馬を引立てて行こうとする。今まで人間の世界と没交渉に、そこらに生えている杉菜を食っていた馬が、急に引立てられることによって、二人の袂を分かつわけになる。
「杉菜喰う」で多少その辺の景色も現れているし、「ひつたつる」という荒い言葉の裏に、送る者の別を惜しむ情が籠っているように思われる。餞別の句としては巧みなところを捉えたものである。
☆☆☆☆
畏友の森銑三の解説が、宵曲の魅力を伝えてくれる。岩波文庫の解説文として白眉の文章。
森銑三 解説文より
『古句を観る』の古句は、元禄時代の無名作家の手になつた俳句ばかりを集めてゐる。それでゐてその個々は今日出しても清新な句ばかりなのだから、元禄時代にかやうな句も出来てゐたのかと驚かされる。宵曲子は古い俳書をも丁寧に読んで、さうした句ばかりを集めてゐたので、その点に子の鑑識が窺はれる。・・子ならでは作ることの出来ぬ書物であつた。
宵曲氏は一歩退いて世を送らうとしてゐた控え目な人で、そのことは一部の人々に知られてゐるのに過ぎない。子は何ともいはれぬ気持ちのよい人で、その実力は子を知る限の先輩同輩の等しく認めるところであつた。
☆☆☆☆☆