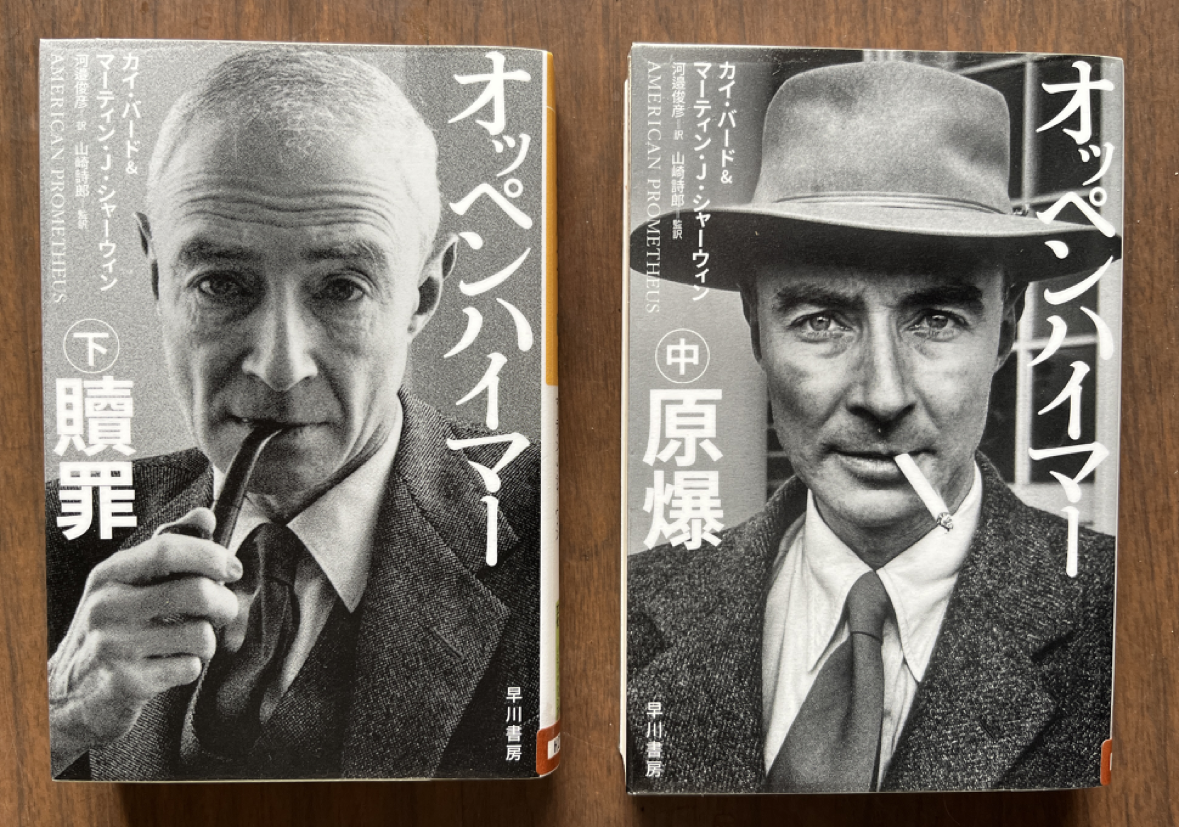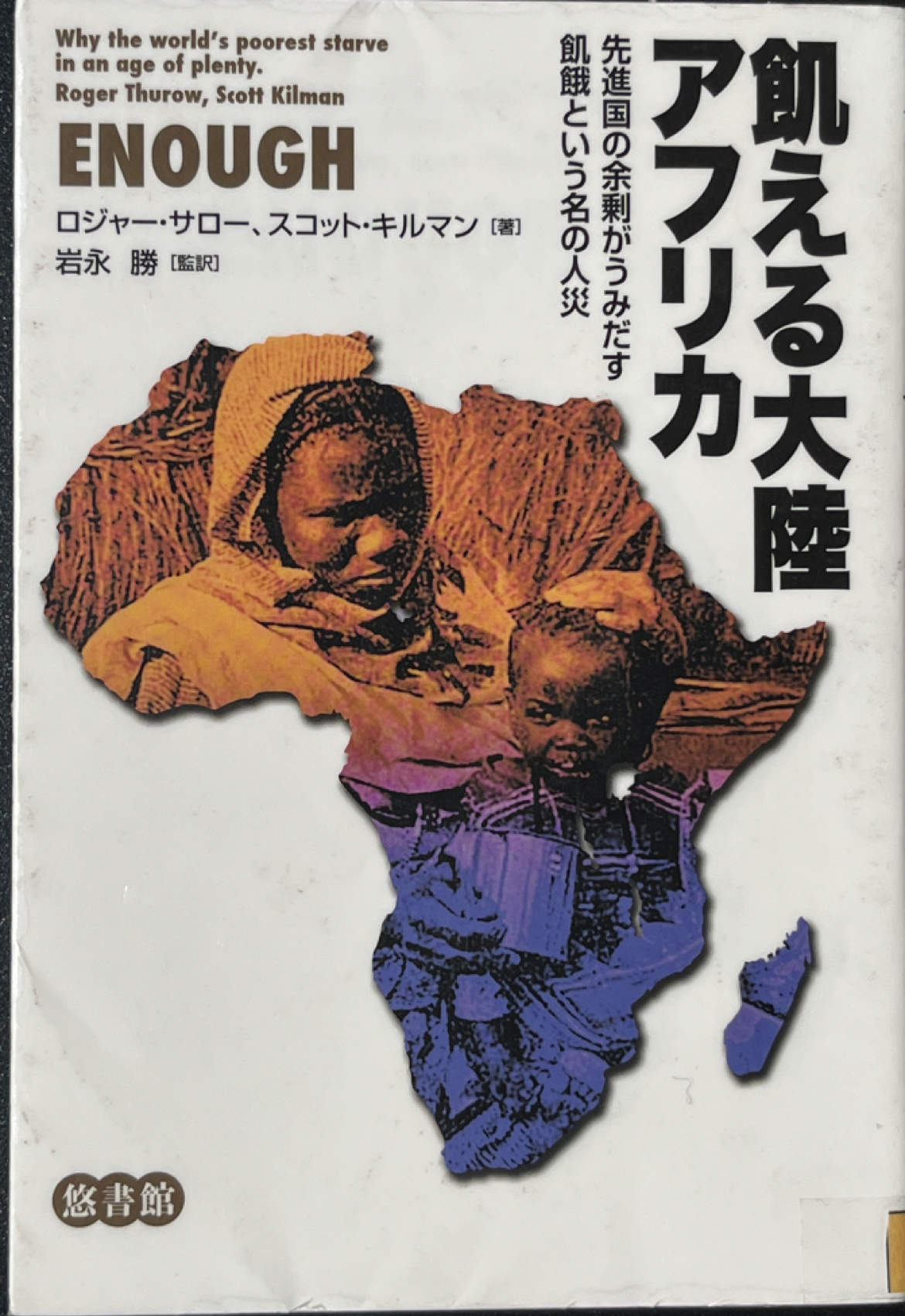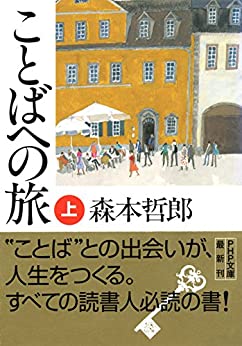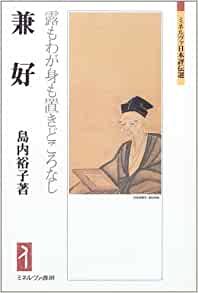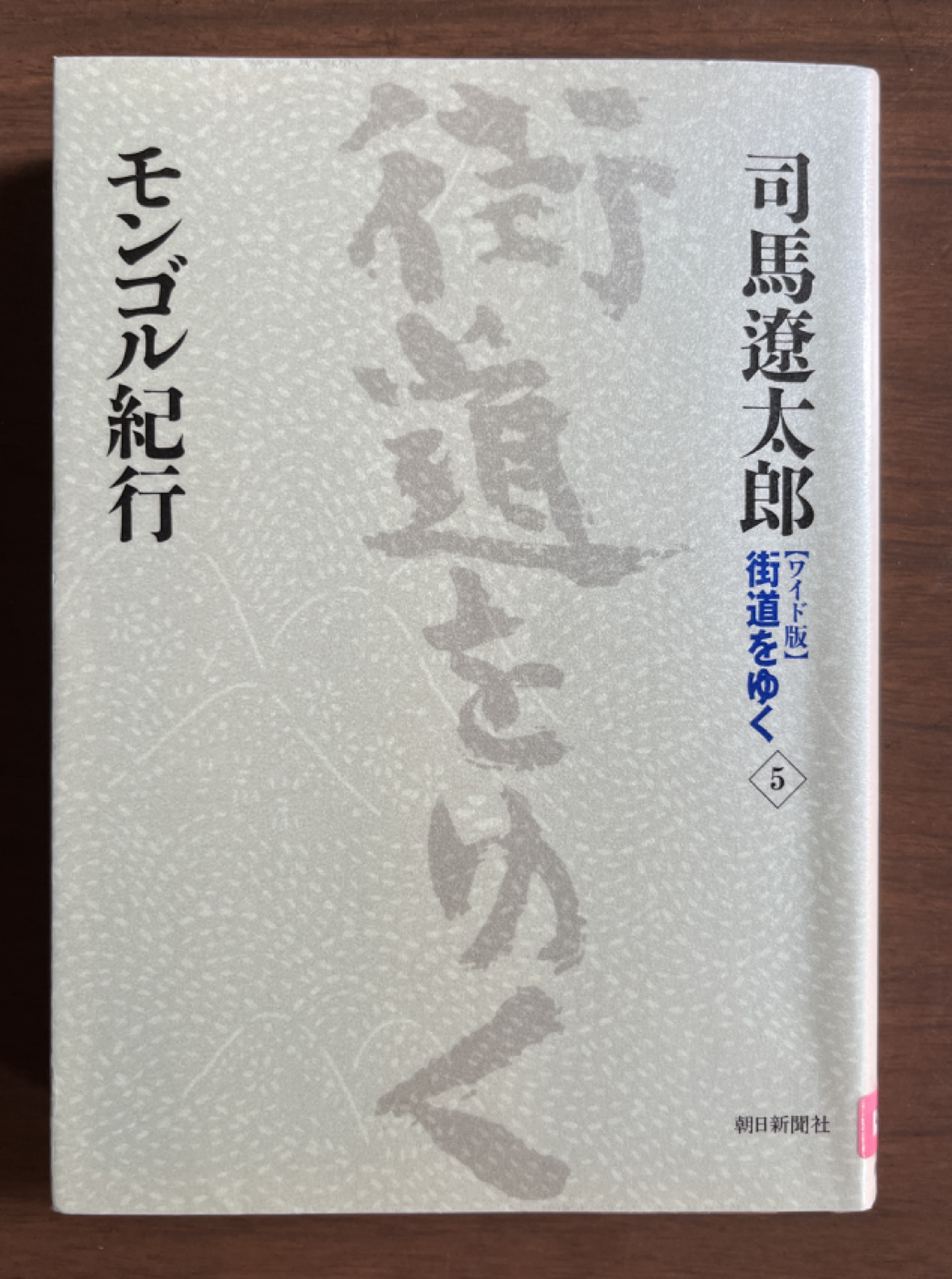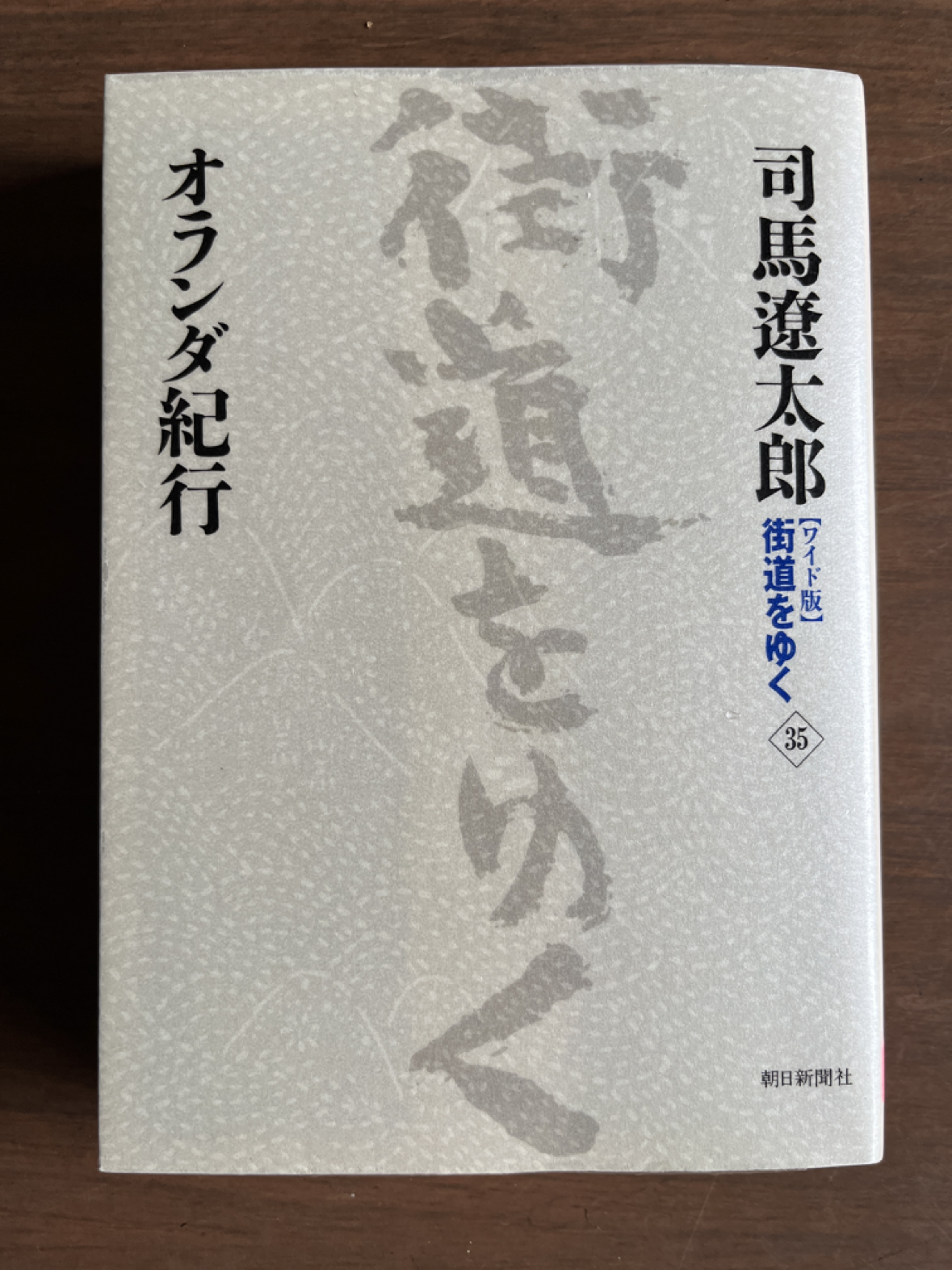読書逍遥第185回 『細胞』(上・下)(その4)ジッダールタ・ムカジー著
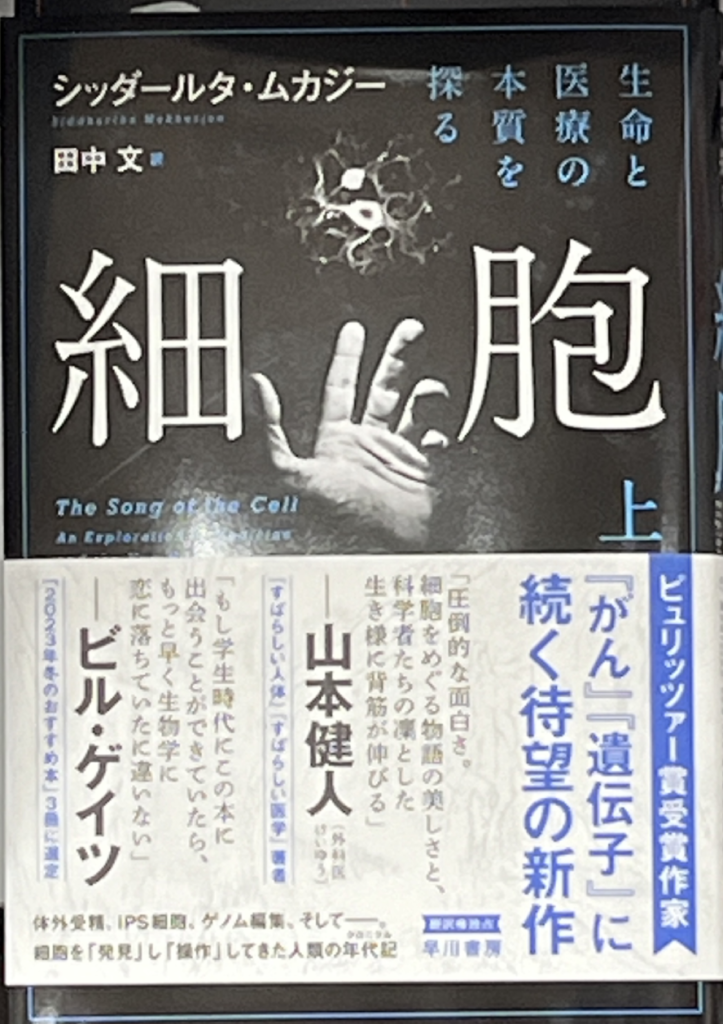


『細胞』(上・下)(その4)ジッダールタ・ムカジー著
副題 生命と医療の本質を探る
原題 The Song of the Cell
An Exploration of Medicine and the New Human
[科学進歩の流れは一定の方向に]
「見えるものの観察」から「見えない物への探求」へ進む(ちょうど解剖学から病理学への発展への流れに見られるように)
17、18世紀の科学は、「目に見える探検・観察・観測」の時代
19世紀に入り徐々に「目には見えないものの探究」に移るようになる。
顕微鏡の発達で肉眼で見えない世界が見えるようになってくる
そこに見られる社会受容プロセスは、次のようになる。
思いがけない観察結果→発表→社会反発→観察積み重ね→新しい考え方(発想の転換)→さらに精緻な観察による証明→社会が常識として受容
「私たちは誰もが、あなたも私も、はじまりは1個の細胞だった。同じ物質的な単位からできている」
原子 遺伝子 細胞
世界は、どれもが基本的な単位で構成されている
「肉」
連続的で、一様で、目に見えるもの
↓
「血」
連続しない、粒子状で、目に見えないもの
「細胞学」 細胞自体の構造に着目
「組織生理学」 細胞同士が協力し合うシステムに着目
○シュワンとシュライデン
見方の転換
ラスパイユ
細胞はなぜ存在しているのか?
細胞は何かの働きをしているに違いない!
レーウェンフック、ラスパイユ、ビシャなど先駆者たちの研究を統合して、根本的な説を出す
→先駆者たちが発見したのは生物全体に当てはまる普遍的な原則なのではないか
「細胞は生物をつくっている」
○ ルドルフ・ウイルヒョー(1821-1902)
二つの原則の確立
①すべての生物は1個かそれ以上の細胞でできている
②細胞は、生物の構造と組織の基本単位である
以前として残る謎
「細胞の起源」細胞はどこから生じるのか?
「真の知識とは、自分の無知に気づくことです」