第18回 小冊子『渡辺崋山が歩いた天保二年の旅』
冨田鋼一郎
有秋小春

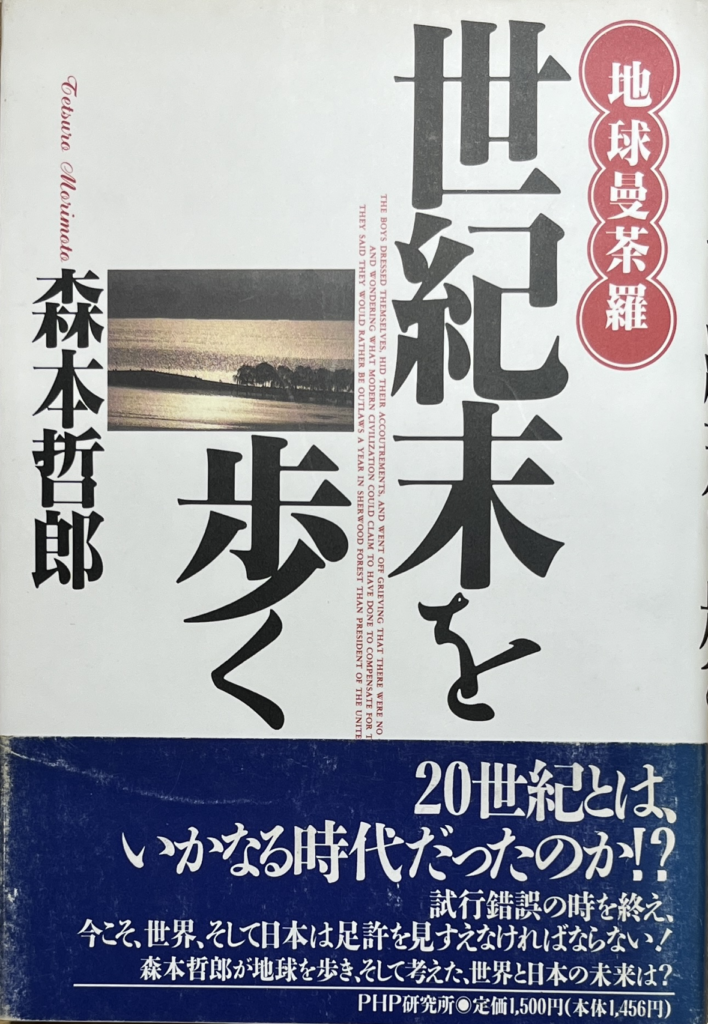
1993年発行
本書が世に出てからもう30年になる。
ベルリンの壁崩壊、ソビエト解体と続いた。東西冷戦が終わり、これで世界は一つになり平和が訪れたと希望を抱いた。
ところが実際にはどうなったか。
改めて世紀末の有り様を思い返して、行く末に思いを馳せる。
☆☆☆
「逍遥」について
逍遥とはゆっくりと歩くこと。
中国の文人たちは、俗世を避けて田園に廬を結ぶと、逍遥のために庭に三本の径(こみち)をしつらえた。
⭕️三径荒(こう)に就くも松菊猶存す
陶淵明
これを念頭に、蕪村は、路に関する詩情豊かな句を作った。
⭕️三径の十歩に尽て蓼の花 蕪村
⭕️路絶て香にせまり咲く茨かな
⭕️我帰る路いく筋ぞ春の艸
⭕️これきりに小道つきたり芹の中
⭕️花茨故郷の路に似たるかな
⭕️極楽のちか道いくつ寒念仏
⭕️桃源の路次道の細さよ冬ごもり
蕪村もこよなく小径を愛した。
ハイデガー『野の道(フェルト・ヴェーク)』には、味わうべき言葉がある。
「野の道では、早春の歓喜と、晩秋の沈黙とが出会い、少年の戯れと老年の知恵が見つめ合う。そして全てがひとつに響き合い、そのこだまを運んでいく。」
「こだまを運ぶ野の道」。美しい句だ。
☆☆☆
道は交通の手段だけにあるのではない。いつの世も、道は思索を誘う。
こんもりした榎の木が道端にあれば、どんなに散歩が愉しくなることか。
家の近くには、二本榎の木があるのを知っている。ひとつは神田川沿い、もうひとつは肥後細川庭園の池のほとり。