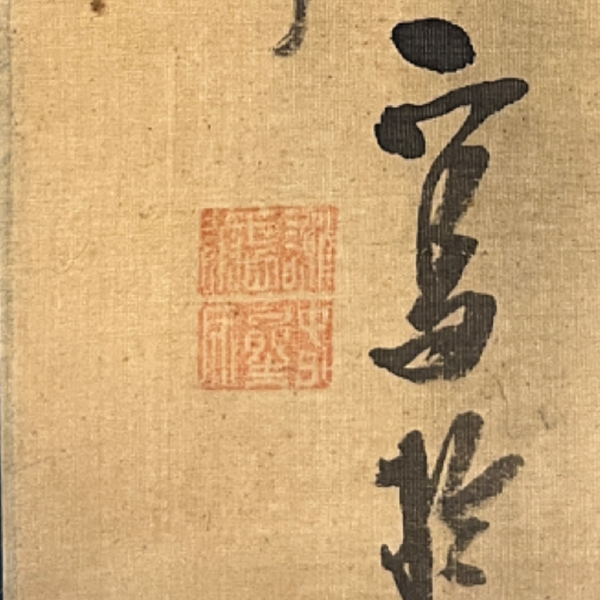芥川龍之介の文章(その3)


短編『手巾(はんけち)』
主人公の長谷川謹造先生は、新渡戸稲造(1862-1933)がモデルといわれる。
「奥さん(新戸部稲造の奥さんはアメリカ人)と岐阜提灯と、その提灯によって代表される日本の文明とが、ある調和を保って、意識に上るのは決して不快なことではない。」
「ヴェランダの天井からは、まだ灯をともさない岐阜提灯が下がっている。そうして、籐椅子の上では、ストリントベルクの作劇術を読んでいる。自分は、これだけの事を書きさえすれば、それが、如何に日の長い初夏の午後であるか、読者は容易に想像のつく事だろうと思う。」
→籐椅子、提灯などがあるベランダ光景は、漱石家を連想させる。
「(小さなテエブルの下に)婦人の手がはげしくふるえているのに気がついた。ふるえながら、それが感情の激動を強いて抑えようとするせいか、膝の上の手巾を、両手で裂かないばかりに緊(かた)く、握っているのに気がついた。」
→ 「気がついた」を繰り返す。小さな、しかし心を揺さぶる発見。
「先生の顔には、今までない表情があった。見てはならないものを見たと云う敬虔な心もちと、そう云う心もちの意識から来るある満足とが、多少の芝居気で、誇張されたような、甚だ複雑な表情である。」
「長い夏の夕暮れは、いつまでも薄明かりをただよわせて、硝子戸をあけはなした広いヴェランダは、まだ容易に暮れそうなけはいもない。」
「先生は、飯を食いながら、奥さんにその一部始終を話して聞かせた。そうして、それを日本の女の武士道だと賞賛した。日本と日本人とを愛する奥さんが、この話を聞いて、同情しない筈はない。先生は、奥さんに熱心な聴き手を見出した事を満足に思った。」
→見事な達意の文章!
→「こんなことがあったよ」。明治の東京人は季節のうつろいにさらされながら暮らしていた。夫婦で交わされるささやかな一場面。これで満ち足りた1日を終える。
→幸田露伴の短編『太郎坊』の夕餉の場面を思い出す。