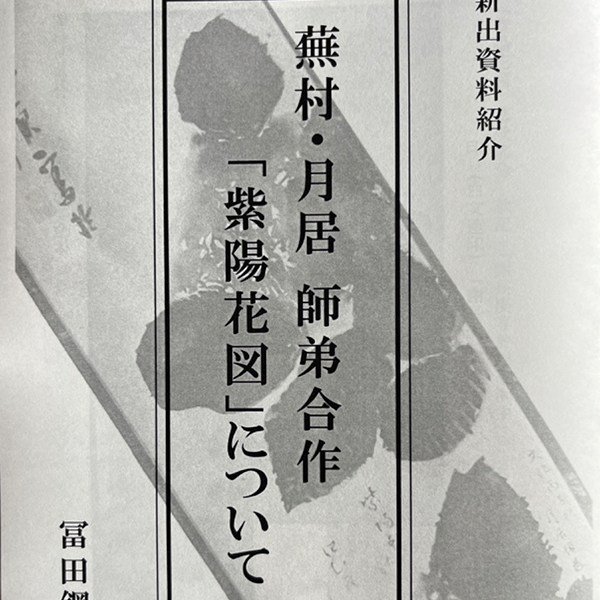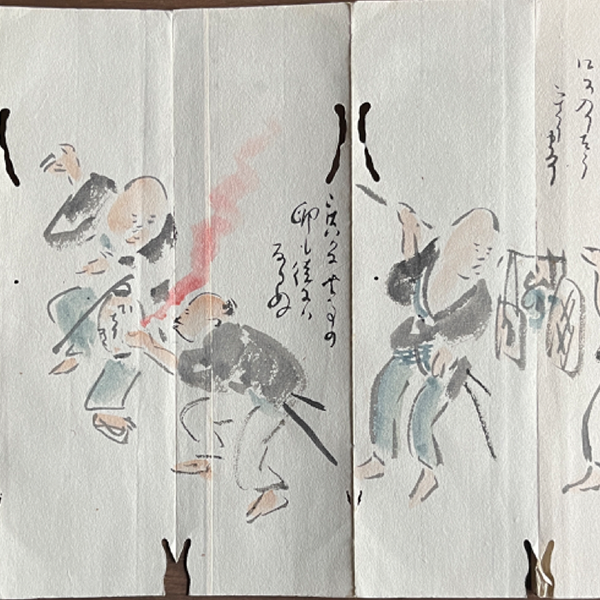漱石『硝子戸の中(うち)』


全編とても透徹とした文章で、ことに末文は絶筆と言っていいほど。
今回目に留まったのは、その少し前の第33章にある。
亡くなる2年前漱石は、人との関わりについてこんな不安や鬱屈した気持ちを抱えていた。随分とペシミスティックだ。
とてもまわりくどい言い方をしているが、意を尽くすにはこう表現するしか手はなかった。よくぞ心の中を曝け出してくれた。
最期にたどり着いた「則天去私」は、きっとこの煩悶が源になっているはずだ。「則天去私」という言葉を得て、この言葉を支えに残された時間を生きていこうとした矢先に命を落としてしまった。漱石は自分の生涯を振り返って満足したのだろうか。どうだろう。
ここに出てくる「片付ける」という言葉も彼のキーワードだ。
自分に刻み込むために、彼の言葉を煩を厭わずここに書き留めておく。
「私は何でも他(ひと)のいう事を真(ま)に受けて、凡て正面から彼らの言語動作を解釈すべきだろうか。もし私が持って生まれたこの単純な性情に自己を託して顧みないとすると、時々飛んでもない人から騙される事があるだろう。その結果陰で馬鹿にされたり、冷評(ひや)かされたりする。極端な場合には、自分の面前でさえ忍ぶべからざる侮辱を受けないとも限らない。
それでは他(ひと)はみな擦れ枯らしの嘘吐きばかりと思って、始めから相手の言葉に耳も貸さず、心も傾けず、或る時はその裏面に潜んでいるらしい反対の意味だけを胸に収めて、それで賢い人だと自分を批評し、また其所に安住の地を見出し得るだろうか。そうすると私は人を誤解しないとも限らない。その上恐るべき過失を犯す覚悟を、初手から仮定して、掛からなければならない。或る時は必然の結果として、罪のない他(ひと)を侮辱する位の厚顔を準備して置かねば、事が困難になる。
もし私の態度をこの両面のどっちかに片付けようとすると、私の心にまた一種の苦悶が起る。私は悪い人を信じたくない。それからまた善(い)い人を少しでも傷けたくない。そうして私の前に現れて来る人は、悉く悪人でもなければ、またみんな善人とも思えない。すると私の態度も相手次第で色々に変わっていかねばならないのである。
この変化は誰にでも必要で、また誰でも実行している事だろうが、それが果たして相手にぴたりと合って寸分間違いのない微妙な特殊な線の上をあぶなげもなく歩いているだろうか。私の大いなる疑問は其所に蟠(わだかま)っている。
÷÷÷÷
今の私は馬鹿で人に騙されるか、あるいは疑い深くて人を容(い)れる事が出来ないか、この両方だけしかないような気がする。不安で、不透明で、不愉快に満ちている。もしそれが生涯つづくとするならば、人間とはどんなに不幸なものだろう。」